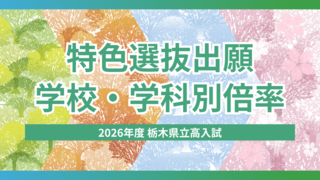若者の県外流出が続く中、「若者に選ばれるとちぎづくり」をテーマに、県が若者から直接意見を聞く「とちぎ若者会議」が始まった。2年間の予定で、本年度は県内13市町と「大学コンソーシアムとちぎ」から推薦された18~29歳の計16人が委員を務める。
人口減少に伴い、次世代を担う若年層の意見は重要性を増す。若者の声を今後の施策に着実に反映させることが必要だ。若者会議からの提言は、部局の垣根を越えて全庁で共有し、市町とも連携して課題解決に当たってほしい。
他都道府県への転出が転入を上回る「転出超過」は、東京、大阪などの大都市圏を除く全国の地方で共通の課題となっている。本県では進学や就職を機に首都圏へ転出する若者、特に女性が多い。
出生率向上や転出超過解消に向けた取り組みを官民連携で進めるため、県は本年度「県人口未来会議」を設置し、対策や宣言を8月にまとめた。民間団体や行政機関の代表者ら計25人の委員が活発な議論を交わしたが、メンバーの中に若年層の代表は含まれていなかった。
人口減少に対応し、未来に向けた対策を進めるには、若者の視点は欠かせない。
若者会議はその役割を果たすはずだ。8月下旬に開かれた初会合には福田富一(ふくだとみかず)知事も出席し、意見を交わした。今後は関係部署の担当者も交えて話し合うという。
会議では公共交通の充実、子育て世代が住みやすい環境整備に向けた提言のほか、若者の起業などを後押しする体制や、若者が当事者意識を持ってまちづくりに参加できる機会の必要性を指摘する意見が相次いだ。
行政がこうした若者の意見に正面から向き合い、政策に反映させることで、若者側の意識が変わる可能性も高い。故郷への愛着や地域社会の一員としての自覚が芽生えるきっかけとなり、ひいては転出超過の抑制にもつながることが期待できる。
県内市町でも高校生らによるまちづくり活動を支援したり、首長と若者が直接、意見を交わしたりする取り組みが広まっている。しかし地域によって温度差がある。
県と市町が協力して、若者会議を地域別に開くことも一案ではないか。将来的には、県政や市政、町政の基本指針策定に、若者が加わる仕組みも検討すべきだろう。
 ポストする
ポストする