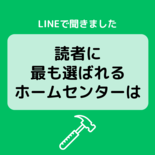大量のデータを学習し、文章や画像を作る「生成人工知能(AI)」。会議の要約やメール文面の添削などをお願いすると、早ければ数秒で回答をくれる。作業の効率化につながる便利なツールだが、なかなか手を出せない人もいるのではないか。下野新聞社は「生成人工知能」に関するアンケートを実施し、利用状況や実際に使った手応えなどを聞いた。
そもそも生成AIとは何か。「一言で分かりやすく説明して」と生成AIに頼むと、「膨大な知識を学習し、全く新しいものをゼロから創り出すAIのことです」と回答が返ってきた。
アンケートは2025年7月31日~8月25日、下野新聞のLINE公式アカウント「とちぽ」で実施し、栃木県内外の10代以下~70代以上の男女923人から回答を得た。
残り:約 1104文字/全文:1445文字
この記事は「下野新聞デジタル」のスタンダードプラン会員・愛読者(併読)プラン会員・フル(単独)プラン会員のみご覧いただけます。
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く

 ポストする
ポストする