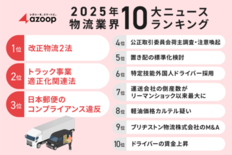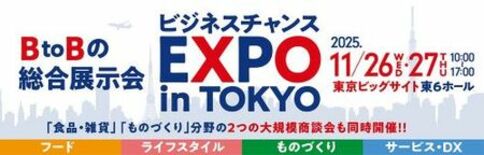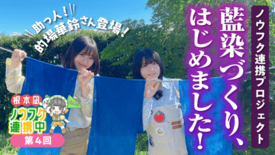高いフレキシブル性能と高い発電性能の両立を実現
2025年10月21日
早稲田大学
局面にフィットする”切り紙型”熱電発電デバイス ~高いフレキシブル性能と高い発電性能の両立を実現~
詳細は早稲田大学Webサイトをご覧ください
【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102172/202509044602/_prw_PT1fl_2UfRx2zR.png】
近年、IoT (Internet of Things) デバイス※1の自立電源として、温度差から電力を得るフレキシブル熱電発電デバイスが注目されていますが、曲げたり伸ばしたりするフレキシブル性能と高い発電性能を両立させることは困難でした。
早稲田大学 理工学術院 岩瀬英治(いわせ えいじ)教授、寺嶋真伍(てらしま しんご)講師(任期付き)らの研究グループは、熱電発電デバイス(Thermoelectric Generator: TEG)※2の新構造として図1のような切り紙構造の一種である「ポップアップ切り紙構造※3」を考案し、フレキシブル性能と高い発電性能の両立を実現しました。具体的には、曲率半径0.1㎜の屈曲変形や1.7倍の延伸変形させることができるにもかかわらず、これまで提案されたフレキシブル熱電発電デバイスの発電能力を凌駕しました。
このことを活かした応用として、曲面熱源であるヒトの体表に貼付し、ヒトの体温と空気の温度差で生じる発電を利用して体温の無線送信にも成功し、これまでにない発電性能を有した熱電発電デバイスであることを実証しました。今後、ウェアラブル機器や医療・福祉分野への応用が期待されます。
本研究成果は、国際学術誌「npj Flexible Electronics」のオンライン版に2025年10月21日に公開されました。
論文名:Pop-up kirigami thermoelectric generator with high stretchability and conformal thermal interfaces
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509044602-O2-P1ag3F1u】
図1 曲げ変形および伸縮変形が可能なポップアップ切り紙型熱電発電デバイス(図中のNはN型の熱電素子を示し、PはP型の熱電素子であることを示す)
キーワード:
切り紙、熱電発電、IoT (Internet of Things)、フレキシブル電子デバイス、ストレッチャブルディスプレイ、ウェアラブル機器、次世代エレクトロニクス
(1)これまでの研究で分かっていたこと
IoTデバイスやウェアラブル機器の普及に伴い、バッテリー交換不要で環境から電力を得られる発電技術が注目されています。中でも、ヒトや配管のような曲面から熱を利用できるフレキシブル熱電発電技術は有望視され、近年、研究が盛んに行われています。
従来の研究において、シリコーンゴムなどのゴム材料を基板材料として適用することで、フレキシブルな熱電発電デバイスは提案されているものの、ゴム材料の熱抵抗が高く発電量を大きく損なっていました。すなわち、フレキシブル性能と高い発電性能にはトレードオフの関係がありました。そのため、材料に依らず構造によってフレキシブル性能を得る方法として、折り紙や切り紙の構造を利用したフレキシブル熱電発電デバイスが注目され始めました。しかしながら、これまでフレキシブル熱電発電デバイスに適用された折り紙や切り紙の構造は、ミウラ折り※4や七夕飾り(天の川)※5の構造といった一般的な折り紙や切り紙の構造であり、熱源への接触が面接触ではなく線接触であったり、大気への放熱面がないなど、熱電発電デバイスには不向きな構造でした。
(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと
本研究では、熱電発電デバイスが抱えるフレキシブル性能と高い発電性能の両立が困難であるという課題を解決するため、新たな切り紙構造である「ポップアップ切り紙構造」を考案しました。
非伸縮性材料の薄いフィルム基板に切り線パターンを施し、平面状態で熱電素子を実装した後、立体的に展開させることで屈曲性・伸縮性を実現させ、多様な曲面熱源への適合性を可能にしました。
性能評価の結果、曲げや延伸といった変形を加えても、フラットな状態と同等の発電性能を維持できることを確認しました。また、曲率半径0.1mmの屈曲変形や1.7倍に伸ばす延伸変形が可能であることを示しました(図2)。したがって、緩やかに曲がった熱源のみならず、90度に曲がった角を持つような熱源であっても貼付可能です。
さらに、開発した熱電発電デバイスを無線送信回路と接続したセンシングの実証では、ヒトの体表に貼付し、ヒトの体温と空気の温度差で発電することで、体温の無線送信実証にも成功し、ウェアラブルIoT機器としての有用性を実証しました。これまで、ヒトの皮膚の体温(34℃程度)と大気(22℃)の温度差から無線送信が可能な電力(100 μW)を得るのは困難であり、本熱電発電デバイスが高い発電性能を有しているといえます。これにより、電池交換や廃棄の必要無しに、血圧や体温などの健康状態をモニタリングすることが可能となります。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509044602-O3-VBAckMIO】
図2 各種変形時の性能計測結果
(3)研究の波及効果や社会的影響
本研究により、従来困難だった「高いフレキシブル性能と高い発電性能を有する熱電発電」が可能となり、IoTデバイスやウェアラブル機器のメンテナンスフリー化が現実となります。
また、以下のような波及効果と社会的インパクトを有しています。
1.エネルギー自立型IoT社会への貢献:
電池交換の不要な自己発電型センサとして、IoTネットワークの信頼性・持続性を大きく向上させることが可能です。特に、センサが多数設置されるスマートシティやインフラモニタリングにおいて、メンテナンスコストの低減と長期運用が期待されます。
2.ウェアラブルヘルスケアの進展:
人体に密着して安定した発電が可能であることから、バイタルサインを常時測定するヘルスケアデバイスへの応用が可能です。患者の体温や状態をリアルタイムで把握することにより、遠隔医療や高齢者の見守り支援にもつながります。
3.災害・非常時の電源確保
やかんなど身近な熱源から電力を得られるため、停電時や災害時にも携帯端末や通信機器の動作に必要な電力を確保でき、非常用電源としての有効性が期待されます。特に電力インフラの整わない地域や緊急避難所などにおいて大きな社会的価値を持ちます。
4.切り紙構造技術の新展開
これまでアートや一部の機構設計に限られていた切り紙技術を、熱設計と融合し、高性能なエネルギーデバイスへと展開した本研究は、複数分野にわたる融合研究の先駆例となります。
(4)課題、今後の展望
本研究で提案したポップアップ切り紙構造は、本研究で用いた細長く硬い熱電素子だけでなく、カーボンナノチューブ(CNT)シートのような薄膜の熱電素子にも適用可能な構造であるため、様々な熱電材料へ展開することが考えられます。さらに、現在のフレキシブル基板で一般的に用いられている、ポリイミド銅基板を基板材料として用いており、立体化の工程以外は現在のフレキシブル基板の製造工程で実現可能なため、量産化・大面積への展開が容易であると考えています。
低コストで製造可能なフレキシブル熱電発電デバイスを開発することで、IoTセンシングデバイスやウェアラブル機器に利用可能な自立型電源を実現できると考えられます。
(5)研究者のコメント
切り紙は、折り紙に比べると国際的な認知度がやや低めではありますが、学術的にも興味深い特徴を多数持っているため、電子デバイスとの相性は良いです。熱電材料のみならず今回提案したように構造についての研究が広く行われ、国際的に広く使用される未来を期待します。
(6)用語解説
※1 IoT (Internet of Things) デバイス
センサや家電、機械などの「モノ」がインターネットにつながり、データを送受信する仕組みを指します。温度や動きなどを自動で測定・制御でき、スマート家電や医療機器、工場の監視装置などに広く使われています。電池交換が難しい場所で使われるため、自己発電機能を備えたIoTデバイスが期待されています。
※2 熱電発電デバイス(Thermoelectric Generator: TEG)
デバイスの両端に与えた温度差に対して、電圧が発生する熱電効果(ゼーベック効果)を利用した発電デバイス。デバイスに生じる温度差が発電量につながるため、温度の高い熱源には密着し、温度の低い大気には良く放熱することが重要である。
※3 ポップアップ切り紙構造
長手方向に圧縮することで高さ方向に立ち上げることのできる切り紙構造であり、電子部品を載せる平らで変形しない面を持ち、構造全体を引き伸ばすことができます。立ち上げ後には、熱電素子が実装された脚部は無変形であるため平面を保ったまま曲げ伸ばしができる構造です。
※4 ミウラ折り
日本の航空宇宙工学者・三浦公亮先生が考案した折り紙構造で、折り紙工学の分野において最も有名な折り紙構造です。折り紙工学における周期的パターン構造の一つで、平面を山折りと谷折りでタイル状に配置することで、1自由度構造として折り畳み・展開できるのが特徴です。人工衛星の太陽光パネルなどに応用されています。
※5 七夕飾り(天の川)
紙などのシート材に規則的で平行なスリットが入った構造で、引き伸ばすことができないシート材であっても、引き伸ばしが可能になります。引き伸ばすと、立体的で規則的な網目状パターンが現れるため、日本の七夕の時期には装飾品として扱われます。
(7)論文情報
雑誌名:npj Flexible Electronics
論文名:Pop-up kirigami thermoelectric generator with high stretchability and conformal interfaces
執筆者名(所属機関名):Shingo Terashima(早稲田大学)*、Eiji Iwase(早稲田大学)
*:責任著者
掲載予定日時(現地時間):2025年10月21日
掲載予定日時(日本時間):2025年10月21日
掲載URL:https://www.nature.com/articles/s41528-025-00454-z
DOI:https://doi.org/10.1038/s41528-025-00454-z
(8)研究助成
研究費名:NEDO先導研究プログラム/未踏チャレンジ
研究課題名:切り紙型熱電デバイスによる自立無線センサシステムの研究開発
研究代表者名(所属機関名):岩瀬英治(早稲田大学)
局面にフィットする”切り紙型”熱電発電デバイス
早稲田大学
10/22 9:02
速報
-
 11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
 11/13佐野の河川敷でクマ目撃
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
 11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
 11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
 11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
 11/13下野市内でサル目撃
11/13下野市内でサル目撃 -
 11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
 11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
 11/13ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる
11/13ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる
 ポストする
ポストする