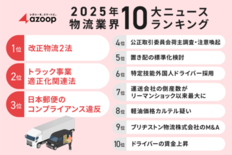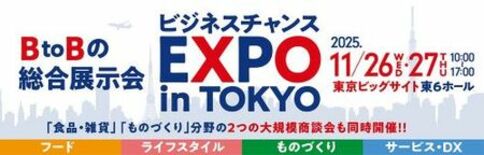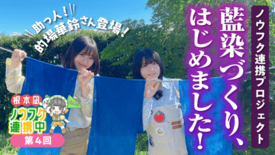医薬品や機能性有機材料の開発を加速する新手法を開発
2025年10月22日
早稲田大学
機械学習で結晶構造の予測精度を2倍に向上 医薬品や機能性有機材料の開発を加速する新手法を開発
詳細は早稲田大学HPをご覧ください。
【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102172/202510227528/_prw_PT1fl_16Ww1c8U.png】
早稲田大学データ科学センターの谷口卓也(たにぐちたくや)准教授、同大学大学院先進理工学研究科一貫制博士課程3年の深澤亮(ふかさわりょう)らの研究グループ(以下、本研究グループ)は、このたび機械学習を使って有機分子の結晶構造予測※1の成功率を向上させることに成功しました。有機分子の結晶構造を予測することは医薬品や機能性材料の開発に重要ですが、膨大な計算コストが課題でした。
本研究では、機械学習を用いて有望な結晶構造の候補を効率的に絞り込み、ニューラルネットワークポテンシャル※2で高速に構造を最適化する新しい結晶構造予測ワークフロー「SPaDe-CSP」を開発しました。本手法を20種類の有機結晶に適用した結果、有機分子の結晶構造を80%という高い成功率で予測することに成功しました。この成功率は従来型のランダムな探索手法と比較して2倍に相当します。本成果は、新たな有機材料の発見を加速させるものです。
本研究成果は、英国の王立科学会が発行する「Digital Discovery」誌にて2025年10月13日(月)にオンライン公開されました。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510227528-O2-cLhs91ao】
キーワード:
結晶構造予測 (CSP) 、有機分子、機械学習、ニューラルネットワークポテンシャル、空間群、探索効率化、材料開発
(1)これまでの研究で分かっていたこと
有機分子の結晶構造は、医薬品の溶解性や安定性、あるいは有機半導体の電気伝導性といった物性に直接影響を与えるため、その構造を正確に予測することは極めて重要です。しかし、有機結晶はファンデルワールス力や水素結合といった弱い分子間相互作用で形成されており、わずかなエネルギー差で多様な構造(多形)を取りうるため、最も安定な構造を予測することは非常に困難でした。従来の予測手法では、考えうる膨大な数の候補構造を生成して一つずつ評価する必要があり、その計算コストの高さが材料開発のボトルネックとなっていました。
(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法
本研究では、この計算コストの問題を解決するため、機械学習とニューラルネットワークポテンシャルを組み合わせた新しい結晶構造予測※1ワークフロー「SPaDe-CSP」※3を開発しました。SPaDeとは、Space group and Packing Density predictorの略称です。分子構造を入力し、結晶の対称性を表す空間群(Space group)と、分子の詰まり具合を示す密度(Packing Density)を予測する2つの機械学習モデルを構築しました。これにより、従来の手法で多数生成されていた、密度が低く不安定な構造候補をあらかじめ排除し、有望な候補に絞って探索を行うことができます。
絞り込まれた候補構造の最適化には、量子化学計算※4に匹敵する精度をはるかに低い計算コストで実現するニューラルネットワークポテンシャル※2を用いました。このワークフローの有効性を検証するため、複雑さが異なる20種類の有機分子の結晶構造予測に挑戦したところ、80%(20種類中16種類)のケースで実験的に観測された構造を正しく予測することに成功しました(図1)。これは、機械学習による絞り込みを行わない従来型のランダム探索に比べて約2倍の高い成功率に相当し、本手法の有効性を実証するものです。一方、分子量が大きく構造が複雑な分子ほど、結晶構造予測が難しい傾向にあることが明らかになりました。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202510227528-O1-p3kdL8wU】
(3)研究の波及効果や社会的影響
本研究で開発された「SPaDe-CSP」は、有機分子の結晶構造予測を大幅に効率化・高速化するものです。この成果は、医薬品開発や機能性材料分野への貢献が期待されます。医薬品の結晶多形(同じ成分でも結晶構造が違うもの)は、溶解性や吸収率、安定性に大きく影響します。本手法を用いることで、製造過程で望ましくない多形が出現するリスクを事前に評価したり、最も安定で効果の高い結晶構造を選択したりすることが可能になり、医薬品開発の効率化に繋がります。また、有機エレクトロニクス※5など、分子の配列が性能を決定する機能性材料の開発において、望みの特性を持つ結晶構造を理論的に探索・設計することが可能になります。これにより、高性能な有機エレクトロニクス材料などの開発が加速されると期待されます。
(4)課題、今後の展望
本研究は結晶構造予測の効率化に大きく貢献しましたが、いくつかの課題も残されています。今回の検証では、分子の形が剛直であるという仮定のもとで計算を行いましたが、実際の分子、特に鎖状の部位を持つ柔軟な分子では、結晶化の際に様々な形(コンフォメーション)を取り得ます。今後は、このような分子の柔軟性も考慮に入れた、より汎用性の高い予測ワークフローへと拡張していく必要があります。また、予測が絶対零度(0 K)での安定性に基づいているため、実用的な温度域での安定性を評価するために、温度効果を計算に組み込むことも将来的な課題です。
(5)研究者のコメント
医薬品や材料の開発には結晶状態を知ることが不可欠ですが、従来の結晶構造予測は計算コストや精度の問題から、誰もが手軽に使えるものではありませんでした。今回開発した手法は、機械学習とニューラルネットワークポテンシャルを組み合わせることで、精度とコストの両面を改善したものです。この技術が、新しい薬や革新的な材料を生み出す一助となることを期待しています。今後は、さらに複雑な分子にも対応できるよう研究を発展させていきたいと思います。
(6)用語解説
※1 結晶構造予測(CSP: Crystal Structure Prediction)
分子の化学構造のみから、その分子がどのような結晶を形成するかを計算機シミュレーションによって予測する技術。
※2 ニューラルネットワークポテンシャル(NNP: Neural Network Potential)
原子間の相互作用エネルギーを、機械学習モデルの一種であるニューラルネットワークを用いて表現する手法。高精度な量子化学計算に近い精度を保ちながら、計算速度を数桁以上向上させることができる。
※3 SPaDe-CSP
空間群と密度を予測する機械学習を用いて結晶構造予測を行う本研究独自の手法
※4 量子化学計算
量子化学に基づき、分子の電子状態や安定構造などを計算機シミュレーションによって解析・予測する手法。機械学習に比べて高精度だが計算コストが高い。
※5 有機エレクトロニクス
有機材料が持つ電子的・光学的機能を利用し、有機ELディスプレイ、有機太陽電池などの電子デバイスに応用する研究技術分野。
(7)論文情報
雑誌名:Digital Discovery
論文名:Crystal structure prediction of organic molecules by machine learning-based lattice sampling and structure relaxation
執筆者名(所属機関名):Takuya Taniguchi*a, Ryo Fukasawab
a-早稲田大学データ科学センター、b-早稲田大学大学院先進理工学研究科
掲載日(現地時間):2025年10月13日(月)
掲載URL:https://doi.org/10.1039/D5DD00304K
DOI:10.1039/D5DD00304K
(8)研究助成
研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究
研究課題名:有機固体材料のマテリアルズインフォマティクス基盤構築(22K14747)
研究代表者名(所属機関名):谷口卓也(早稲田大学)
研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究
研究課題名:機械学習によるHOF材料の安定性シミュレーション(24K17748)
研究代表者名(所属機関名):谷口卓也(早稲田大学)
研究費名:科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 ACT-X
研究課題名:機械学習を活用した有機固相転移の計画的創出(JPMJAX23DD)
研究代表者名(所属機関名):谷口卓也(早稲田大学)
研究費名:住友財団 環境研究助成(一般研究)
研究課題名:効率的な結晶構造予測による有機多孔質材料の構造探索(2432210)
研究代表者名(所属機関名):谷口卓也(早稲田大学)
研究費名: 企業共同研究
研究課題名: Matlantisを利用した分子性固体材料の構造予測とその実験的実証
研究代表者名(所属機関名):谷口卓也(早稲田大学)
機械学習で結晶構造の予測精度を2倍に向上
早稲田大学
10/22 14:00
速報
-
 19:14宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに
19:14宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
 19:03佐野の河川敷でクマ目撃
19:03佐野の河川敷でクマ目撃 -
 18:47真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警
18:47真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
 18:20駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕
18:20駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
 17:50「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性
17:50「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
 17:15下野市内でサル目撃
17:15下野市内でサル目撃 -
 16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる
16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
 16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能
16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
 16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる
16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる
 ポストする
ポストする