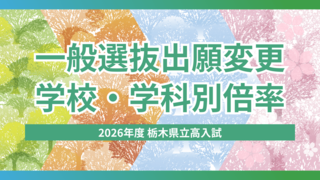クラシック音楽の三大コンクールの一つ「ショパン国際ピアノ・コンクール」が10月、ポーランドの首都ワルシャワで開催された。数あるコンクールの中でも最大の注目度を誇るショパンコンクール。会場のフィルハーモニーホールにはチケットを求めて大勢の人が列をなし、YouTubeのライブ中継にはさまざまな言語で応援メッセージが飛び交う。2度目の出場で栄冠をつかみ取ったアメリカのエリック・ルーは、参加の理由を問われ「キャリアアップが目的」ときっぱり語った。なぜピアニストたちは自ら熱狂の渦に飛び込むのか。何がこのコンクールを特別なものにするのか。現地取材から探った。(取材・文 共同通信=田北明大)
▽音楽に順位「複雑な気持ち」
2015年の前々回で4位に入賞し、その後もピアニストとして数々のオーケストラとの共演やCD録音の経験を積んでいる27歳のエリック・ルー。そんな彼ですら再挑戦の意欲にかき立てられるほど、ショパンコンクールによって得られる名声は特別なものだった。
未明にずれ込んだ審査結果の発表から一夜明け、ワルシャワ市内のホテルで開かれた記者会見。ルーは、音楽で順位を競うという矛盾について「複雑な気持ちがある」と吐露しつつ、こう語った。
「残念ながら音楽界は競争が激しく、コンサートができる場所も限られている。コンサートの録音に比べてコンクールにははるかに多くの人が注目する。これは人間の本性だと思う。人々はなぜか競争を好むんです」
普段クラシック音楽を聴かない人でも高い関心を持つショパンコンクール。知名度の向上に大きく貢献したのが、高画質高音質でネットに配信するライブ中継だ。特に2021年の前回大会では、新型コロナ禍でさまざまなコンサートや人が集まるイベントが中止になったこともあり、視聴数が急激に増加。多くの人がスマートフォンやパソコンの画面越しにお気に入りの出場者の演奏を見守った。
従来のYouTubeに加え、今回は若者に親しまれるTikTokでも配信。主催する国立フレデリック・ショパン研究所のアルトゥル・シュクレネル所長は「このコンクールをきっかけとして、世界中のクラシック音楽の愛好家が集まる場を作りたいと思っているのでうれしい」と、関心の高まりを歓迎する。
▽出場回数制限も検討
課題も浮かび上がった。例えば出場者同士のキャリアの差をどう考えるかだ。実際、現地入りしたある音楽関係者は本選が始まる前の段階で「優勝はエリック・ルーだろう」と予測していた。一方、才能を感じさせてもコンサート経験が少なく、実力を発揮しきれない出場者がいるのも確かだ。
シュクレネル所長は共同通信などのインタビューで「前回も本選に出場している30歳の人と初めて出場する16歳の人では経験に差があり別世界。比べられるかどうかが問題だ」と指摘。出場回数の制限を設けるかどうかを検討していると明かした。「若手ピアニストの登竜門」という性質を主催者としてどのように考えるか。さらなる議論が求められそうだ。
出場者の多くが中国系を始めとするアジア人だったことも印象的だった。84人の出場者のうち国別で最多は中国の28人。アメリカやカナダ国籍の中国系のピアニストの活躍も目立った。
審査員の1人で、1980年にアジア人として初めてショパンコンクールで優勝したベトナム出身のダン・タイ・ソンは「今の中国は、まるで30年前の日本のように教育の水準が非常に高く、外国からも教師が訪れ、本格的に指導している。ショパンは感情を込めて弾く必要があるが、中国の人たちは感受性が豊かで良いバランスを保っていて、非常に自然に演奏する」と評価した。
シュクレネル所長も「中国の人たちはレベルが高い」と評価。一方、出場者のレベルが全体的に高くなっていることが予備予選前のビデオ審査の判定を難しくしているとして、今後はビデオ審査をやめ、各地域ごとに予備予選を実施して出場者を決める方法をとる可能性があることも示唆した。
▽ひときわ人気の2人
出場者の演奏を通して、これまで気が付かなかったショパンの音楽のさまざまな側面に触れられるのも醍醐味だ。特に今回の入賞者は、ショパンの音楽を自分たちなりに解釈しながら自由に個性を発揮し、「自分の音楽」を披露できたピアニストがそろったと感じる。
エリック・ルーはまさに曲そのものに深く入り込むような思索と精神性に満ちたショパン。3次予選では体調不良で演奏順が変更されるなど心配な面もあったが、本選で披露したピアノ協奏曲第2番は、ショパンの若書きの作品とは思えないほど味わいのある情感豊かな演奏で、聴衆を圧倒した。
今大会でひときわ聴衆の人気を集めた2人は4位に選ばれた。本選後に誕生日を迎え17歳となった中国のリュー・テェンヤオは、星の形のキラキラ輝く髪飾りを付けて出場。舞台に登場すると場がぱっと華やぐスター性を兼ね備えながら、演奏は極めて自然体。会場で出会ったある音楽関係者が「あまりにも全てが完璧でむしろ怖さを感じる。絶対に実演を聴いた方が良い」と漏らしたほど。
本選で披露したピアノ協奏曲第1番の軽快な第3楽章は、思わずこちらも体を揺らしてしまうような華やかさと喜びを感じる演奏だった。結果発表後にホールの外で「あなたの演奏は良かった」と伝えると、「ありがとう」と日本語で返されたのも印象的だった。
▽骨太のショパン
リュー・テェンヤオと同率で4位入賞した桑原志織はスケールの大きい骨太のショパンで聴衆をくぎ付けにした。元々はリストやブラームスといった重厚な曲を得意とする桑原。今大会でもバラード第4番やピアノ・ソナタ第3番などの大作で持ち味を存分に発揮した。本選で披露した「幻想ポロネーズ」は確固たる意思を感じる地に足付いた演奏で、特に速度を速める終盤の迫力は圧巻。隣に座っていたメディア関係者が小声で「すばらしい」とささやいていたのが聞こえ、ピアノ協奏曲第1番の演奏後は立ち上がって拍手を送る人もいた。地元のポーランド人からの評価も高く、「上位入賞は間違いない」と太鼓判を押す人もいた。
「個性的」という言葉が最もふさわしかったのは5位入賞のマレーシアのヴィンセント・オン。音色やフレーズの歌い方が独特で、決して派手ではないものの不思議と癖になる演奏。聴き続けるうちにすっかりとりこになった、という人も少なくなかったはずだ。はっきりとしたタッチで弾き進めていくピアノ協奏曲第1番は、強弱や緩急といった表現が巧みで、普段意識しない音や響きの面白さも気付かされるような立体感のある演奏。次はどうなるんだろうとわくわくしながら聴き、ショパンの音楽の新たな可能性を見いだしてくれたようにも感じた。
▽普遍的で多様性があるショパン
ショパンの音楽への考え方を一層深めたピアニストも。5位に選ばれ、日本にも何度も演奏に来ているという地元ポーランドのピョートル・アレクセイヴィチは、結果発表後の記者会見で「ショパンをますます人間として捉えるようになった。彼は人間の人生の本質を理解し、あらゆる感情や心情を音楽に込めたということを発見した」と語った。
「踊りとしてのポロネーズやマズルカを習得しているポーランド人は大勢いるが、だからといってポーランド人が他国の人より優れた演奏をするかというと違う。ショパンの音楽は普遍的で多様性がある。重要なのはピアニストの出身ではなく、作品が生まれた背景や文脈を学び、全体像を知ることでショパンの個性に近づくことだ」
6位のウィリアム・ヤン(アメリカ)も結果発表後の会見で「過酷だったが楽しむこともできて、結局はすべて報われたと思っている」と振り返り、次のように続けた。
「ありがたいことに、ショパンの音楽は本当に飽きることがないんだなと気がついた。今も以前と同じくらい愛している。彼の音楽は人間の感情の全スペクトルを網羅していると思う。音楽が持つ内なる強さと同時に彼が常に持っていた弱さもさらけだすことが大切だと思う」
× ×
「クレッシェンド!」は、若手実力派ピアニストが次々と登場して活気づく日本のクラシック音楽界を中心に、ピアノの魅力を伝える共同通信の特集企画です。
 ポストする
ポストする