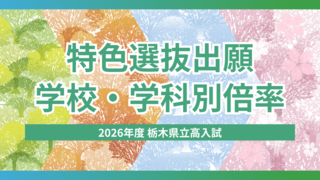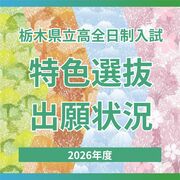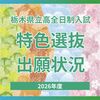増加する不登校児童生徒の支援を一層充実させるため、県教委は本年度、フリースクールなどの民間支援団体や医療・福祉部門との連携体制構築に向けた協議に乗り出した。不登校児童生徒の社会的自立に向けて、関係機関の現状や課題を共有し、協力体制づくりを促すという。
学校とそれ以外の機関の垣根を越えた連携強化への大きな一歩となる。それぞれの強みを生かし、着実に支援の手が届くよう、県教委が主導し、子どもを中心に据えた連携体制を築いてほしい。
県内公立校の昨年度の不登校児童生徒は、小中学校で過去最多の5983人となった。高校は1033人と、前年度を上回った。
県教委が昨年度実施した不登校に関する調査では、原因不明の体調不良や家族関係の問題など、学校だけでは解決が難しいケースが少なくなかった。一方、教員の約4割は民間の支援機関の機能の違いが分からないと答えた。
地域にどのような支援機関や居場所があり、どう連携できるのか。情報交換をするため県教委は本年度、関係機関を集めた初めての協議会を開催した。10月には県内各地の教育事務所や市町教委、フリースクールなどの支援団体や県・市町の保健福祉分野の担当者ら約80人が集まり、それぞれの役割を確認した。
今後は地域ごとに、学校と関係機関の担当者が顔を合わせる場を設ける必要があるだろう。さらに実際に連携を進めるには、個人情報を含む情報共有や、学校によって判断が分かれるフリースクールなどの出席認定の在り方など、解決しなければならない課題もある。
重要なのは、不登校の子どもや親が孤立することを防ぐことだ。県教委の昨年度の調査では、支援機関を利用せず「自宅のみ」で過ごしていた児童生徒は4~5割程度に上った。支援機関が家庭訪問して学習を支援する仕組みなども検討してはどうか。
子どもが不登校になったことで、保護者が仕事を辞める「不登校離職」も深刻な問題になりつつある。収入減によって生活が困窮すれば、福祉的支援も必要になる。
学校と地域の支援機関の連携は、子どもの貧困や自殺対策など不登校以外の対応にも有効に働くだろう。スクールソーシャルワーカーなど専門職の充実も求められる。
 ポストする
ポストする