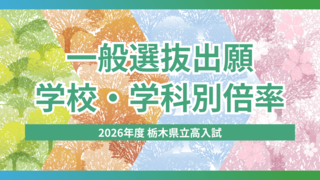足尾銅山鉱毒事件の解決に奔走した田中正造(たなかしょうぞう)の旧宅(佐野市小中町)で案内役を務める女性団体「旧宅説明ボランティアの会」の活動が、正念場に立たされている。30年にわたり尽力してきたが、高齢化などに伴い会員数はピーク時に比べ半減した。関係者は「若い世代に引き継げなければ将来的に継続は難しい」と危機感を募らせる。
地球規模で環境悪化がますます進む中、文明社会の在り方に警鐘を鳴らす正造の思想を学ぶ意義は大きい。案内役の活動はその機会を創出しており、重要度も増している。関係者とともに行政が主体となって次世代の育成などに注力すべきだろう。
正造は死の直前、旧宅を古里の小中村(当時)に寄贈した。農業振興と教育の拠点として活用してもらうことが願いだった。遺志の継承を誓った村民は1913年、「小中農教倶楽部(くらぶ)」を設立。旧宅の維持管理や、正造とカツ夫人の法要を行っている。
会は旧宅の一般公開が始まった93年に合わせ、市民らで発足させた。女性団体としたのは、社会的に女性活躍を後押しする狙いもあったという。発足当初からの70代会員は「来場者とお互いに語り合うことで正造の遺徳を継ぐ場になっている」と語る。
今では旧宅の事業に不可欠な存在となったが、高齢化による退会や新型コロナ禍の影響で新規会員の募集が停滞。2014年には30人超だった会員は14人にまで減少した。近年は活動時間も短縮せざるを得ない状況となっている。
手をこまねいている訳ではない。倶楽部と市は今秋、新たな人材を育成する講座を開いた。若い世代にも参加してもらおうと、講座の受講対象を「高校生以上」と明記し、市内の各高校などにも呼びかけた。しかし生徒や学生の参加はゼロだった。
正造の顕彰団体を巡っては、県内で中核的な役割を担ってきた市民団体「田中正造大学」が22年、活動に幕を下ろした。研究団体の草分けとされる「渡良瀬川研究会」(群馬県館林市)も同年、半世紀の歴史に幕を閉じた。
もはや団体個々の努力で後継者を確保するのは難しくなっている。佐野市などが旗振り役となり、後継者不足の現状を広く発信する必要があるのではないか。機運を高め、正造の遺産を継承していく必要がある。
 ポストする
ポストする