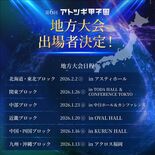~高精度の量子制御を実現~
2025年11月19日
早稲田大学
数アト秒精度で2つのアト秒レーザーによる波動関数の干渉を測定 ~高精度の量子制御を実現~
詳細は早稲田大学HPをご覧ください
【表:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102172/202511199380/_prw_PT1fl_4yVzUF19.png】
早稲田大学理工学術院 新倉弘倫(にいくらひろみち)教授とカナダ国立研究機構・オタワ大学のDavid Villeneuve博士らの研究グループは、数アト秒精度での測定が可能な、2つのアト秒レーザーパルスを用いた新たな波動関数の量子干渉測定法を開発しました。この方法により、ヘリウム原子の極端紫外領域にある、高い電子状態の波動関数の174アト秒周期での時間発展を測定しました。数アト秒からゼプト秒領域で起こる現象の測定や、新たな量子材料の測定・量子制御法への展開が期待されます。
本研究成果は、2025年11月10日にPhysical Review A誌にオンライン掲載されました。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O2-579DhcgQ】
図1. ヘリウム原子の4pリドベルグ準位の、174アト秒周期での電子波動関数の位相変化。2つのアト秒レーザーパルスの時間差を変えて測定。
キーワード:
アト秒レーザーパルス・波動関数・量子コヒーレント制御・極端紫外領域
(1)これまでの研究で分かっていたこと
様々な物質の性質や化学反応、分子構造などは、分子や物質中の電子が重要な役割を果たしています。高次高調波発生※1による極端紫外領域のアト秒レーザーパルスを用いることで、これらの電子や分子の変化だけでなく、電子の量子的な性質をアト秒時間領域(1アト秒=10のマイナス18乗秒)で測定することが可能になっています。
近年、新倉らの研究グループは、アト秒レーザーパルスと赤外レーザーパルスを用いて、イオン化された複素数の電子波動関数のイメージングに成功しました。一方、2つの同じアト秒レーザーパルスを用いる方法も試みられていますが、高い時間精度で2つのパルスの時間差を制御し、さらに同じ場所に集光して電子の運動量分布などを測定するには、複雑かつ高価な測定システムが必要でした。
(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと、そのために新しく開発した手法
本研究では新たに、簡単な光学系を用いた、2つのアト秒レーザーパルスによる電子波動関数の干渉測定法を開発しました。
これまでの、1つのレーザーパルスを2つに分けて用いる方法(図2(a))では、干渉計の機械的精度やゆらぎのため、2つのパルス間の時間差の高安定での制御や、測定試料への照射方法に課題がありました。そこで本研究では、異なる波長の2つのレーザーパルス(赤外レーザーパルスωと紫外レーザーパルス2ω)を用いて、同じ光学経路上でアト秒レーザーパルスAとBとを発生させました(図2(b))。同じ光学経路を用いるため、光学経路の違いによるゆらぎが存在せず、容易にアト秒レーザーパルスAとBとの時間差を高い精度で変えることができます。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O3-O1IBiojW】
図2.(a)従来の方法。赤外レーザーパルスを2つにわけて、2つのアト秒レーザーパルスを発生させる。(発生したアト秒パルスを2つに分ける方法もある)。(b)今回の方法。赤外レーザーパルス(ω)と紫外レーザーパルス(2ω)を時間的に離し、2つのアト秒パルスを同じ光学系路上で発生させる。このとき、通常のアト秒パルス発生の原理とは異なり、14ωの両端に13ω, 15ωという“余分の”高調波が発生する。この余分の高調波を測定に利用する。
アト秒レーザーパルスは、複数の異なる波長からなる高調波を含んでおり、高次高調波とも呼ばれます※1。波動関数の干渉を測定するためには「同じ波長の高調波」が必要ですが、赤外レーザーパルスから発生したアト秒レーザーパルスAと、紫外レーザーパルスから発生したアト秒レーザーパルスBは、通常のアト秒パルス発生の原理によれば、同じ波長の高調波を含んでいないとされています。ところが今回、赤外レーザーパルスと紫外レーザーパルスの時間間隔を適切に制御すると、アト秒レーザーパルスBには“余分な”高調波(図2(b)の13ω, 15ωなど)が含まれていることがわかり、そこで、AとBとに含まれる、同じ波長の高調波15ωを利用した波動関数の干渉測定方法を開発しました。
具体的には、まず1つ目のアト秒レーザーパルスBで、ヘリウム原子の高い電子状態(4pリドベルグ準位)に電子波動関数を生成しました。この電子波動関数は複素平面を時間発展し、位相成分が連続的に変わります※2。次に100フェムト秒(fs)ほどの時間間隔をあけて、2つ目のアト秒レーザーパルスAを照射し、同じ波動関数を生成しました。さらにAとBの時間差をわずかにアト秒だけずらすと、2つの波動関数が重なり合う条件が変わり、時間差に応じて波動関数同士の強めあいと弱めあいが起こります。(コヒーレント制御※2)。その重なり合った波動関数を、赤外レーザーパルス(IR)によるイオン化過程で検出しました。図1はアト秒レーザーパルスAとBとの時間差を変えたときの、イオン化により生じた光電子の収量の変化を示しています。174アト秒周期での光電子の収量の振動は、4p状態の電子波動関数の位相が、この周期で振動していることに対応しています。また、100フェムト秒以上の間、電子波動関数の量子的なコヒーレンスが保たれていることも示しています。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O4-U5eOTISm】 図3.測定の方法
この方法では、レーザーパルスを2つに分けて、再度、重ね合わせるという干渉計を用いていないため、高い時間精度および安定度で、2つのアト秒レーザーパルスの時間差の制御が可能になります。補足として、同じ測定系を用いて新たに測定した波動関数のコヒーレント制御の結果を、次の動画で示します。
(https://niikura.w.waseda.jp/mov/NiikuraHe2510A.mp4)
ΔTは2つのアト秒パルスの時間間隔を変えるときの時間ステップ、Tは相対的な2つのアト秒レーザーパルスの時間差です。この測定では時間ステップサイズが700ゼプト秒(1ゼプト秒=10-21秒)から増加しており、この方法を用いて、ゼプト秒時間間隔での測定の応用も期待されます。
(3)研究の波及効果や社会的影響
アト秒レーザーパルスは、従来の放射光源よりもはるかに小型の極端紫外・軟X領域の光源として期待されています。また、コヒーレント光源であるため、複数のレーザーパルスとの組み合わせが容易であり、電子波動関数の位相などの量子的な情報を得ることができます。一般に、アト秒領域の実験では精密に光学系を制御する必要がありますが、一方でこのことが、アト秒レーザーパルスを用いるときの課題の一つとなっています。本研究で用いる方法では、数アト秒精度での測定が容易なため、アト秒レーザーパルスの応用を広げることができます。
また同様の方法を、分子や固体、表面に適用することで、物質の新たな量子力学的性質や、化学反応における波動関数の変化などの測定法の開発につながります。量子コンピューターでは、様々な電子状態の計算を行うことが目的の一つですが、計算結果との比較対象・検証のために高精度な実験結果を得ることが将来的に期待されます。
(4)課題、今後の展望
本研究で用いたヘリウム原子の4pリドベルグ状態では、電子波動関数の位相変化は174アト秒周期ですが、測定の精度は数アト秒以下も可能です。そこで、数アト秒からゼプト秒で生じる新たな物理現象を発見し、測定することが今後の課題となります。
(5)研究者のコメント
異なる波長から発生したアト秒レーザーパルス(高次高調波)は、これまでの常識では、発生する波長は異なるはずでしたが、今回、同じ波長が発生しうるということを波動関数の量子干渉の実験を通じて示すことができました。また、もし赤外レーザーパルスと紫外レーザーパルスを時間的に完全に重ね合わせてアト秒レーザーパルスを発生すると、2つのパルスの干渉により発生するアト秒レーザーパルスが変動するため、このような測定は出来ません。いろいろと意外性のある結果だと思います。最近、論文と同じ方法・装置を用いてどの時間ステップで測定ができるかを試してみましたが、今回の方法は良い精度で測定できることがわかったため、ゼプト秒への展開が楽しみです。
(6)用語解説
※1 高次高調波の発生
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O6-FDPCP78X】 図4.アト秒レーザーパルス(高次高調波)の発生方法
※2 位相成分・コヒーレント制御
固有状態の波動関数は【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O7-g5S9M28q】 という式に従い、複素平面内を時間【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O8-419AN4pe】 の関数として時間発展(位相【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O9-y5kve45Q】 が変化)する。ここで【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202511199380-O10-OR1lh5Ba】 は、基準となるエネルギー準位からの相対的なエネルギー差で、この実験では、ヘリウム原子の基底状態1sと4pリドベルグ状態とのエネルギー差に相当する。異なる時間で生成した2つの波動関数が重なると、この位相成分が重なり合い、強めあいまたは弱めあいが起こる。このように波動関数の重なりを制御することをコヒーレント制御(coherent control)という。アト秒レーザーパルスにより、極端紫外領域のコヒーレント制御が可能になった。
(7)論文情報
雑誌名:Physical Review A
論文名:Attosecond wavepacket interferometry using two-color XUV pulses
執筆者名(所属機関名):Hiromichi Niikura (早稲田大学 理工学術院・教授) *、D. M. Villeneuve (カナダ国立研究機構、オタワ大学)
掲載日時:2025年11月10日(月)
掲載URL:https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/zwlz-c743
DOI:https://doi.org/10.1103/zwlz-c743
(8)研究助成
研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A)
研究課題名:アト秒高分解能位相イメージング波動関数測定法による多電子光イオン化の研究(課題番号:23H00290)
研究代表者名(所属機関名):新倉 弘倫(早稲田大学)
研究費名:日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的研究(開拓)
研究課題名:固体での新規アト秒位相分解ARPES分光法の開発(課題番号:24K21241)
研究代表者名(所属機関名):新倉 弘倫(早稲田大学)
数アト秒精度で2つのアト秒レーザーによる波動関数の干渉を測定
早稲田大学
11/19 14:00
速報
-
 19:26SNSグループで投資を勧められ… 鹿沼の70代男性が1030万円被害
19:26SNSグループで投資を勧められ… 鹿沼の70代男性が1030万円被害 -
 19:09真岡で震度4【栃木県内各地の震度】
19:09真岡で震度4【栃木県内各地の震度】 -
 15:46太陽光発電設備販売のウェルビング(宇都宮)に破産手続き開始決定
15:46太陽光発電設備販売のウェルビング(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
 12:18すしデリバリーのPEAK’S(宇都宮)に破産開始決定 人気ラーメン店を以前に経営
12:18すしデリバリーのPEAK’S(宇都宮)に破産開始決定 人気ラーメン店を以前に経営 -
 12:14そば店経営のつち家(足利)に破産開始決定 朝そば、トロトロそば湯で集客
12:14そば店経営のつち家(足利)に破産開始決定 朝そば、トロトロそば湯で集客 -
 11:21平口法相、栃木刑務所廃止の方針明らかに 地域との関係評価 「苦渋の決断」
11:21平口法相、栃木刑務所廃止の方針明らかに 地域との関係評価 「苦渋の決断」 -
 9:31患者搬送中の救急車が物損事故 宇都宮
9:31患者搬送中の救急車が物損事故 宇都宮 -
 12/11警察官が作った書類を破った疑い 那須烏山の30代男を逮捕
12/11警察官が作った書類を破った疑い 那須烏山の30代男を逮捕 -
 12/11「先生のおかげで利益」は嘘だった… 那須塩原の40代女性が200万円被害
12/11「先生のおかげで利益」は嘘だった… 那須塩原の40代女性が200万円被害
 ポストする
ポストする