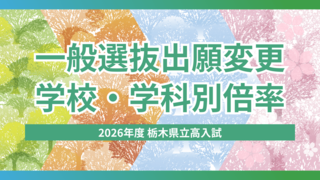全国ワーストだった本県の男女間賃金格差が、2024年は44位とわずかに改善した。だが女性の賃金は男性の74・0%にとどまっており、依然格差が大きいことに変わりない。全国平均も75・8%で、格差解消は全国的な課題といえる。
県は本年度、格差是正につなげようと企業への支援金支給事業を始めた。産業構造の特徴など格差がつきやすい事情はあるものの、官民挙げたより一層の取り組み強化と、企業側にはもう一段上の努力を求めたい。
男女間賃金格差は、男性の賃金を100として女性の賃金を数値化したもので、厚生労働省が公表している。フルタイム労働者の賃金を基に算出しており、最大は静岡県の73・1%。愛知県が73・7%で続き、最も格差が小さいのは沖縄県の83・4%だった。
24年の本県男性の給与の平均額は34万6800円で全国9位。女性は25万6800円で13位だった。男女とも上位の水準にあるが、割合では44位に低迷している。
本県は、男性の正社員が多く賃金水準が高い大企業の工場が立地するなど製造業が主力産業であることが一因とされる。また女性は結婚や出産で退職することが少なくなく、男女で勤続年数に差があることや、男性に比べ女性は正規雇用が少ないことも格差につながっている。
既に多くの企業で取り組んでいるが、出産後や育児中も働き続けられる環境整備は不可欠だ。さらに時短労働など制約がある働き方を前提に、勤務時間を柔軟にするなど働き方改革を一層進めたい。
県内企業の賃上げと格差是正につなげようと、県は賃上げ加速・定着支援金事業を始めた。5%以上の賃上げと、女性管理職比率の改善など企業内の男女間格差是正に取り組むことを条件に支給する。県内の中小企業や小規模事業者は利用を前向きに考え、是正を図ってほしい。
一方、栃木労働局は賃上げ支援に関する特別相談窓口を設置している。賃金格差の原因が分かる厚労省の分析ツールもあり、積極的に活用し自社の経営に生かすべきだ。
就業者数の減少が避けられない中、人材確保は今後さらに厳しさを増すだろう。環境変化に柔軟に対応し、生産性の向上などに取り組むことで競争力のある体質となることが企業には求められる。
 ポストする
ポストする