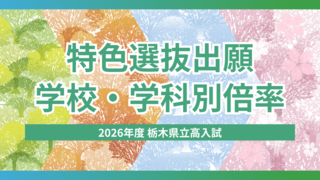4月から使用される教科書を見ると、小学4年生の算数に「がい数」が登場します。概数(がいすう)はおよその数字のことで、新聞に驚(おどろ)くほど使われています。
まず新聞の中から数字を探します。次にその数字が実数(じっすう)なのか概数なのか考えます。「約(やく)」や「およそ」が付いていないものでも概数がたくさんあることに気づかせます。分からない子どもには、教師(きょうし)や保護者(ほごしゃ)が教(おし)えましょう。
次にどういうものに概数や実数が使われているか、また概数や実数の良い点を考えさせます。新聞の場合、特に「見出し」に概数を使っていることが多く、それがひと目で分かりやすくするためだということを理解(りかい)させましょう。
2月26日付の下野新聞1面には、昨年10月の国勢調査(こくせいちょうさ)の内容が掲載(けいさい)されました。本文では10月1日時点の栃木県の総人口を「200万7014人」と記述していますが、見出しは「200万7000人」と概数を使っています。
人口について語る時も、ほとんどの人は約200万人、約200万7000人と言うでしょう。実数で覚(おぼ)えている人はそうは多くないはずです。このように生活の中では実に概数が多く使われているのです。
 ポストする
ポストする