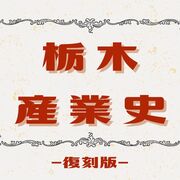昭和基地(きち)から直線距離(ちょくせんきょり)で南へおよそ20キロ、陸上(りくじょう)生物豊(ゆた)かな沿岸露岩域(えんがんろがんいき)「ラングホブデ雪鳥沢(ゆきどりさわ)」でモニタリング調査(ちょうさ)を行った第63次南極地域観測隊(なんきょくちいきかんそくたい)の富山(とやま)県立大講師(こうし)、中澤暦(なかざわこよみ)隊員を紹介します。
南極では、生物の生態系(せいたいけい)・環境(かんきょう)がほとんど手つかずのまま残(のこ)されています。南極大陸はその98%が氷に覆(おお)われていますが、残りの2%は地面がむき出しの露岩域です。
中澤隊員は、そんな露岩域の生物に注目しています。生物といっても、ペンギンやアザラシではなく、とても小さな生き物たちです。
南極の露岩域では、夏に気温が零度(れいど)以上(いじょう)になり、雪がとけるわずか1、2カ月の間にバクテリアや菌類(きんるい)、植物ではコケ類、地衣(ちい)類、藻(ソウ)類、動物ではダニやトビムシ、クマムシやワムシ線類などの原生生物を見ることができます。とても厳(きび)しい環境の中でやっとの思いで定着している南極のこれら陸上生物たちは、環境のほんのわずかな変化(へんか)でも大きな影響(えいきょう)をうける可能性(かのうせい)があるのです。
ラングホブデ雪鳥沢には、数多くのユキドリが生息しており、その名前の由来となっています。ここでは、ユキドリの排泄物(はいせつぶつ)、トウゾクカモメに食べられてできた死骸(しがい)などが、雪どけ水でできた川に流(なが)れ込(こ)み、それを栄養源(えいようげん)として豊かな生態系がつくられています。また、ユキドリ営巣地(えいそうち)を中心とする岩上には、コケなどの群落(ぐんらく)が発達(はったつ)しています。そういった場所のコケの生え方などの変化を観察(かんさつ)するため、サンプルを採取(さいしゅ)したり、デジタルカメラを使って長年にわたり決められた場所でコケの生え方を撮影(さつえい)したりして変化をとらえようとしています。
また、昭和基地の建物周辺(たてものしゅうへん)でも人間の活動が南極の環境にどのような影響を与(あた)えているのかを調べるために、70カ所以上の場所で土壌(どじょう)を採取しました。日本に帰国してから、その試料(しりょう)を分析(ぶんせき)して、環境への影響を調べます。
環境調査は、長い間、地道な調査を積(つ)み重(かさ)ねることで、その変化を知ることができるのです。

 ポストする
ポストする