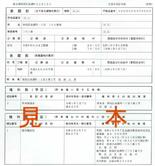「バザーで売る品物が集まらなくなった」。広島市東区のボランティア団体の悩みを紙面で紹介したところ、中国新聞編集局に「うちも困ってます」との声が中区の奉仕団体の女性(67)から寄せられた。不用品の売買はインターネットでもできる時代。バザーは時代にそぐわなくなってきたのだろうか。それとも、まだ可能性を秘めているのだろうか。
声を寄せた女性は打ち明ける。「近年は中元や歳暮の品が集まりにくく、奉仕活動の資金を賄うのが難しくなっている」。新型コロナウイルス禍で昨年は秋のバザーを3年連続で見送った。経済活動再開の動きもある中で、今年は会員や企業から品物を募る従来のやり方で続けるべきか、迷っているという。
全盛期の3分の1
東区の福祉施設で昨年秋に開かれたバザーでは、品数が全盛期の1990年代後半の3分の1程度にとどまった。会場を訪れた同区の主婦鵜飼博子さん(68)は「10年前は人がいっぱいで品物を取り合う雰囲気もあったけれど、今はすいている」と変化を語る。
南区の公務員女性(31)は「欲しい物が少ない」とぼやきつつ「逆に品物を出してと言われたら困る」とわが身を省みた。歳暮や中元を贈り合う習慣はなく、スマートフォン一つで簡単に不用品を売買できるフリマアプリ大手メルカリのサービスを愛用。「メルカリで売り、売れなかったら捨てる。家にバザーに出せる不用品なんてない」
記者も友人の結婚式の引き出物でもらうのは決まってカタログギフト。欲しくない物が送られてくるミスマッチはない。
インターネット上では、バザーへの違和感をつづる書き込みも散見される。「バザーに出す物がなくてわざわざタオルセットを買いに行った」「品物を集めて値札を貼る準備を考えたら、各家庭から数百円の寄付を募った方がいいのでは」といった具合だ。
もはやバザーは時代遅れなのか。そういえば、同じく対面で不用品を売買するフリーマーケットも一時期ほどは見かけない。なぜだろう。日本フリーマーケット協会(大阪市)の藤本浩司さん(47)はネット売買の台頭でフリマ開催数や出展者数は全盛期の80、90年代の3分の1程度に減ったと話す。一方で「対面で会話を楽しみながら売り買いしたいとのニーズは健在。バザーも同じではないか」と見立てる。
出品は気負わずに
取材を続けると「品物は集まってますよ」と話す主催者にも出会えた。昨年10月下旬、公民館まつりでバザーを開いた瀬野学区体育協会(安芸区)。事務局長の大林美恵子さん(58)は中元や歳暮の品は集まりにくいと予想し「『いい物を出そうなんて思わず、なんでも持ってきて』とハードルを下げる呼びかけをした。それが良かったのかも」と明かしてくれた。
雑誌付録のポーチや酒のおまけグラス、景品でもらった企業の名前入りエコバッグ…。「これ売れるのかな?」と思った品が意外に売れ、コロナ前と同等の収益が得られたという。大林さんは「来場者にも満足してもらえた」と喜ぶ。
時代の流れとともに形を変えつつあるバザー。皆さんはバザーに何を期待しますか。
(中国新聞)

 ポストする
ポストする