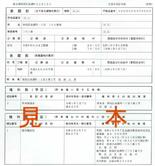岸田文雄首相は20日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを、今春に季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げると表明した。引き下げによって、どのような違いがあるのか。感染症法上の措置や政府の動きをまとめた。
感染症の分類とは
そもそも、感染症はどのように分類されているのか。
感染症法は、重症化リスクや感染力に応じて、感染症を危険度の高さから「1類」から「5類」までに分類している。
1類…エボラ出血熱、ペストなど
2類…結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)など
3類…コレラ、細菌性赤痢など
4類…A型肝炎、マラリアなど
5類…季節性インフルエンザ、梅毒など
新型コロナウイルスは現在、「2類相当」で患者や濃厚接触者の行動制限など最も幅広い措置が可能な「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられている。
「5類」に引き下げられれば、感染症法上の位置付けでは、季節性インフルエンザと同等ということになる。
「5類」の措置とは
では、「5類」とは、感染症法でどのような措置の対象になるのか。

①入院勧告
現状)入院措置や勧告ができる
↓
5類)入院措置や勧告はできない
②外出自粛要請
現状)感染者の隔離、濃厚接触者の外出制限が可能
↓
5類)感染者の隔離、濃厚接触者の外出制限はできない
③就業制限
現状)感染者などに対する就業制限ができる
↓
5類)感染者などに対する就業制限はできない
④入院場所
現状)指定医療機関
↓
5類)一般医療機関
⑤医療費
現状)公費負担
↓
5類)自己負担あり
ただ、新型コロナの「5類」引き下げに関しては、経過措置として当面は公費負担を継続するとみられている。
マスクの着用は
感染防止対策として広まったマスクの着用については、どうなるのか。
政府は「5類」引き下げに合わせて、新型コロナウイルスの感染対策として推奨されている屋内でのマスク着用を、原則不要とする見直し案を検討している。
政府は昨年5月に「基本的対処方針」を改定。マスクに関し、屋外は会話をしなければ原則不要とする一方で、屋内は距離が確保でき、会話をほとんどしない場合を除いて着用を推奨している。
岸田首相は20日、マスク着用の考え方についても見直す考えを明らかにした。
大きな転換点に
岸田首相は20日、関係閣僚と官邸で協議し、春の「5類」引き下げに向けて準備を進めるよう指示した。移行の具体的な時期についてはまだ決まっていない。
厚生労働省の専門家組織は11日、「5類」引き下げの方向に関して、入院調整機能の維持や、患者に過剰な費用負担とならない治療の提供などが必要だと指摘し、「段階的に移行することが求められる」との見解を公表した。
国内で初の感染者が確認されてから3年。政府の新型コロナ対策は大きな転換点を迎えている。

 ポストする
ポストする