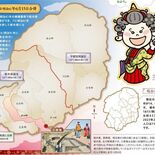なぜ「栃木」と呼ばれるようになったのでしょうか。最初の県庁が栃木町(現栃木市)にあったからなのですが、その栃木町の語源については主に四つの説があります。
(1)町内の神明宮の屋根にある千木と鰹木を遠くから見ると10本の千木に見えたことから「十千木」と呼ぶようになった(2)トチノキがたくさんあった(3)巴波川の崩壊地を表す「チギ」に接頭語「ト」が付いた(4)古代の皇族が遠津木と名付けた-です。
「栃」は、読んだり書いたりするのが難しいですね。下野新聞社1階ロビーには下野新聞の前身、明治時代の「栃木新聞」のコピーが展示してあります。題字を見ると「杤」と「栃」が使われています。
栃木県ができた当時、「栃」は「橡」「櫔」「𣜜」といくつもの字が使われていたそうです。漢字は中国から伝わりましたが、「杤」は日本で作られた国字といわれます。字がたくさんあると混乱するので、県は1872年と79年に「栃」で統一するよう通知しました。
栃木市では6月10日、「県名発祥の地『十千木縁日』」が開かれます。田島大実行委員長(53)は「県名発祥の地『十千木』として、盛り上げるように頑張ります」と話しています。

 ポストする
ポストする