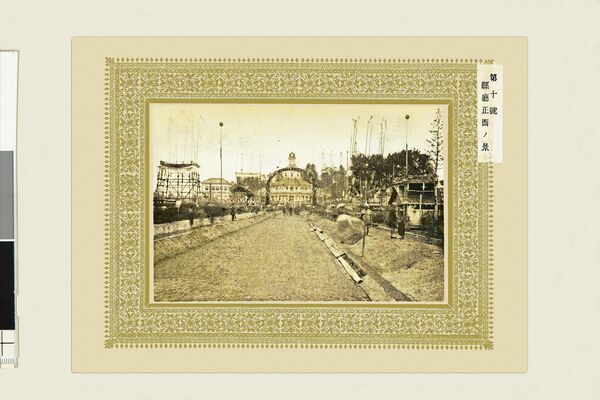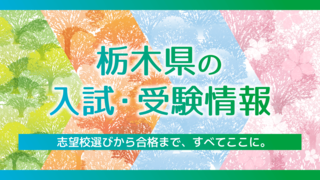「神代より荒れし那須野を拓(ひら)きつつ 民栄えゆく里となさなん」
那須連山の山麓に広がる那須野が原。1881年6月、水にも困る「不毛の地」と呼ばれた地域で和歌が詠まれた。作者は三島通庸(みしまみちつね)。開発への強い思いを歌に込めた三島は、後に第3代栃木県令(知事)に就き、この地の開拓の祖となる。
「土木県令」の異名で知られる三島は就任翌年の84年、栃木町から宇都宮町への県庁移転を断行した。陸羽街道(国道4号)や塩原新道(国道400号)など県内交通の大動脈も整備していく。
特に県北地域の都市開発に尽力。那須疏水の開削、那須野が原の開墾に力を注いだ。強力に土木工事を進め「鬼県令」とも言われた三島だが、那須野が原博物館の松本裕之(まつもとひろゆき)館長(58)は「まさに本県のインフラのベースを築いた」とたたえる。
那須塩原市内には今も「三島」の地名が残り、三島をまつる神社では毎年、例大祭が催されている。
■ ■
73年の本県誕生以降、県知事は初代鍋島貞幹(なべしまていかん)から現職で第56代の福田富一(ふくだとみかず)氏まで、計42人が就任。官選知事は第36代の池田清志(いけだきよし)まで続いたが、1947年4月の第1回統一地方選で、実業家の小平重吉(こだいらじゅうきち)が初の民選知事に選出された。小平の就任第一声は「ガラス張りの明るい県政」。戦後民主主義が幕を開けた瞬間だった。
小平は敗戦直後の食糧難や就職難の対応、カスリーン台風や今市地震など相次ぐ災害からの復旧に取り組んだ。一方で五十里ダムや日光いろは坂、県総合運動公園など現在まで残る重要な施設整備にも奔走した。
■ ■
84年から4期にわたり知事を務めたのは、元農水事務次官の渡辺文雄(わたなべふみお)。今の「イチゴ王国」の礎となる首都圏農業や北関東自動車道整備、「県民の日」制定など幅広い政策を推進した。
渡辺に長く仕え、林務部長で退職した山崎美代造(やまざきみよぞう)さん(87)=宇都宮市下岡本町=は、こうした功績を認めた上で、別の一面にも光を当てる。
バブル経済時代、県北地域で国際的な大規模スキー場などの開発計画が持ち上がり、渡辺は推進すべきか思い悩んでいた。
「スキー場などの計画はやらない。その他のプロジェクトも必要最低限にする」。当時、地域振興課長だった山崎さんが主張すると、渡辺は目をつむり、無言で受け入れた。
「もし進めれば自然破壊者として禍根を残しただろう」。山崎さんは、開発を推し進めずに本県の豊かな自然を守った点も評価されるべきだと強調した。
現職の福田氏は、渡辺の期数を上回る歴代最多の5期目。渡辺のまいた種を着実に形にするとともに、近年では県総合スポーツゾーンを整備し、本県で42年ぶりとなる国体も成功させた。
国体を一過性で終わらせず、スポーツの大規模大会の誘致を通じて地域活性化を図る戦略づくりなどを進めている。歴代知事と同様、後世につながるレガシー(遺産)をどれだけ残せるかが福田県政の課題だ。

 ポストする
ポストする