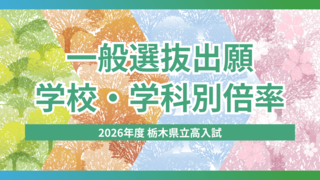栃木県内一の米どころ-。那須扇状地の肥沃(ひよく)な土壌と、那珂川水系の豊富な水に恵まれた大田原は、昔から米作りが盛んな地域だった。
明治期には開田が進められ、米麦を中心とした農業生産は一段と増加した。大正時代には平成の大合併前の旧市域で水稲生産が7500トンを超えるようになり、1920年には9336トンの大豊作となった。
戦中戦後の食糧不足の時代、畑作から稲作・水田化への転換が進んだ。一粒でも多くの米を作るため、各集落では農事研究会などの設立が盛んになり、地下から水をくみ上げる揚水ポンプの普及台数は旧市域内の旧町村の合計で47年の227台から、55年には698台に増加。地域一帯が水田一色になった。
70年ごろからは「量から質」への転換が図られるように。同時に大型機械の導入や土地改良なども進み、量も含め確固たる地位を築き上げていった。
2019年の米を含む市内の耕種農業産出額は84億円で県内1位。県北産米は、食味ランキングで「特A」「A」認定の常連だ。一方、米農家に限らず農業を担う人材の確保は課題の一つ。市内の基幹的農業従事者数は10年の5364人に比べ、20年には4083人にまで減少した。
農業を次世代につなぐため、新たな取り組みを始めた人もいる。花園の米農家の15代目西岡智子(にしおかともこ)さん(47)は4月に農泊施設を開業した。「ご先祖様も課題に直面した時、時代に合わせて対応してきたはず。若い世代には農家の“暮らし”も含めて伝えていきたい」と話す。先人たちが培ってきた米農家の精神は、現代にも引き継がれている。

 ポストする
ポストする