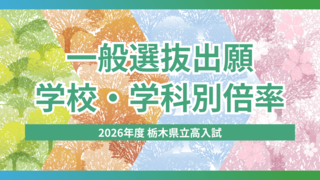壬生町おもちゃのまち。そのユニークな名前は1965年に日本の玩具産業の発展を目的に完成したおもちゃ団地協同組合(約38万5千平方メートル、54企業)に由来する。
同組合の資料によると、62年に東京下町の金属玩具産業が国内外で年々増加する生産量に対応するため、壬生町に進出を決定。同年に輸出玩具工場団地協同組合が設立され、2年後に工場団地造成と東武鉄道住宅団地の整備が始まった。
おもちゃのまちは同組合の歴史でもある。65年、東武宇都宮線に「おもちゃのまち駅」が新設。73年には団地内の進出企業が35社、総従業員は約1500人、生産額100億円を超えた。87年には同組合の名称をおもちゃ団地協同組合に変更。周辺には獨協医大も開学し、人口も増え「おもちゃのまち」が完成した。
ドルショックやオイルショック、リーマンショックなどで玩具業界は再編が進み、工場の多くは海外に移転。団地内の玩具メーカーはエポック社とタカラトミー、バンダイの3社となり、現在は製造や流通、小売業など多業種で構成されている。
同組合は「互助の精神」で発展してきたといえる。団地内の玩具企業は、組合共同倉庫を整備し玩具生産施設も共有するなど、協力体制を築き、技術や生産の向上にもつなげた。
「おもちゃイズム」とも呼ばれる精神は、同組合の初代理事長でトミー工業社長(当時)富山栄市郎(とみやまえいいちろう)氏の考えだった。「創設当時から会員企業が家族的な互助関係の下でおもちゃイズムを受け継ぎ、時代の変化に対応してきた」と同組合の栃木卓夫(とちぎたかお)専務理事は説明する。

 ポストする
ポストする