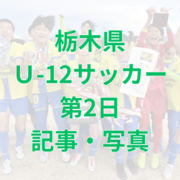矢板市は国道4号、JR宇都宮線、東北自動車道、東北新幹線といった南北を貫く「大動脈」が通り、交通の要衝と呼ばれる。その歴史は何段階かをへて今日の姿になった。
江戸初期は今市と大田原を結ぶ日光北街道が中軸で、道沿いに矢板宿があった。1695年に福島・会津若松と氏家の間に会津中街道が開削され、東西と南北の街道が交差した。
続く明治期の変化が最も大きい。1884年の新陸羽街道(旧国道4号)開削と86年の宇都宮-黒磯間の鉄道開通だ。東京と東北地方を結ぶメイン道路が奥州街道から移り矢板を貫く。同年矢板駅、99年には片岡駅が開業。市教委の津野田陽介(つのだようすけ)学芸員(40)は「国道と鉄道完成後、まちは南北に発展した」と話す。
道路や鉄道の建設は地元の実業家矢板武(やいたたけし)(1849-1922年)が大きな影響を与えたとされる。本町の矢板家正門にぶつかる予定だった旧国道4号の計画が矢板の要望で一夜にして変更されたとの逸話が残る。
第2次大戦後は1968年国道4号バイパス開通、73年に東北道矢板インターチェンジが完成し市の産業発展に大きな影響を与えた。鹿島町などで給油所を営むヤマグチ2代目山口博之(やまぐちひろゆき)社長(63)は「旧国道4号は長距離貨物車、バイパス完成後は乗用車がひっきりなしに往来し、向かいの自宅に渡るに渡れないほどだった」と振り返る。
2000年代は11年の県道矢板那須線バイパス、21年に矢板北スマートインターチェンジ(IC)が開通。道の南北軸が充実する中、市は今年、同ICと「国道4号矢板大田原バイパス」の接続などを目指し県と検討を開始、新たな東西軸強化に動き出している。

 ポストする
ポストする