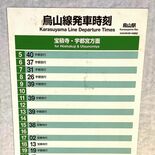存続の危機を何度も乗り越え、真岡鉄道の今がある。
1912年に下館(茨城県)-真岡駅間が開通し、18年に七井駅(益子町)、20年に現在と同じ茂木駅まで延びた。戦後、経済成長に伴い利用者が少ない路線の廃止が全国で相次いだ。国鉄真岡線も類に漏れず、60年代以降、廃線計画が浮上しては「生活の足を守れ」と芳賀郡市各地で住民の反対運動が繰り返された。
87年に県や沿線市町、企業が出資する第三セクター方式による存続が決まり、88年4月、新生真岡鉄道としてスタートを切った。それまで廃止を阻止しようと、官民一体となった回数券購入の運動が広がり、市の広報に地区別の購入率が載るほどだったという。
94年3月には地域活性化の夢を乗せ、70年を最後に姿を消していた蒸気機関車(SL)が復活した。「沿線自治体の人々の心を結ぶSLに」。当時の下野新聞には、導入に尽力した当時の菊地恒三郎(きくちつねさぶろう)真岡市長の言葉が残る。
昨年6月、SLの乗客数が100万人に達し、来年3月には運行30周年を迎える。SLはイチゴと並ぶ真岡市の「顔」になっている。
真岡鉄道総務課の竹前直(たけまえあたる)さん(29)は、SLと“同級生”。物心ついたときから西田井駅で手を振った。真岡鉄道に関わりたくて2018年、他業種から転職して入社した。「本当に地域に支えられているのを実感しています」
利用者は7割超が高校生。少子化は進み、SLの維持管理には多額の費用がかかる。相変わらず環境は厳しいが、2年前には真岡鉄道応援団ができた。地元密着で奮闘するローカル線を愛する住民はまだまだいる。

 ポストする
ポストする