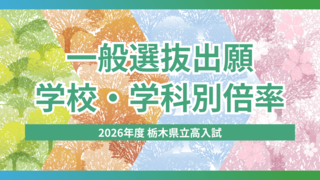青く染まった手は、数多くの生地を染めてきた職人の証しだ。
染料作りから下塗り、染色など多くの工程が必要になる藍染め。特に染色は腕の見せどころで、経験を頼りに染液に漬ける時間や回数を調整する。
「思い通りの色合いを出せるか。腕を試されるが、やりがいも感じる」
唯一無二の伝統色に染まったバッグやのれんは、上品で落ち着きのある印象を放つ。
2024年に創業220年を迎える黒羽藍染め店「紺屋」の8代目店主。創業時は、材木店で働く職人のはんてんを中心に作っていたという。
高校卒業後、家業を継ぐため東京都江戸川区の職人の下で藍染めの基礎を学んだ。技術が身に付くにつれ魅力を感じ、染めの世界にのめり込んでいった。
修業を積んでいた24歳の時、先代が他界。若くして紺屋を継いだ。「まだ学ぶことがあり不安だった」と当時の心境を振り返る。
かつて5軒ほどあった黒羽藍染め店も、現在は紺屋を残すのみとなった。注文依頼は全国から舞い込む。「代々続いてきた黒羽藍染めを後世に残したい」。技術に磨きをかける日々は続く。
黒羽藍染 1804年に紺屋の初代新兵衛(しんべい)から始まった。大豆の汁に松煙墨と呼ばれる墨を入れ、下染めをする。これにより一般的な藍染めよりも色が濃く、生地が丈夫に仕上がる。
 ポストする
ポストする