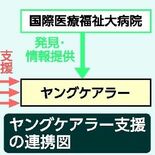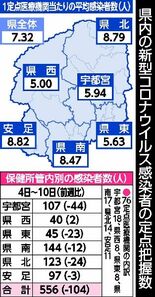大人に代わり家族の世話や介助をする「ヤングケアラー」への理解を深めてもらおうと、県は14日までに啓発動画を作成し、動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開を始めた。ドラマや経験者へのインタビューを通じて、表面化しにくいヤングケアラーの実態や、周囲が気付くことの大切さを伝えている。
啓発動画は中高生向けと大人向けの全2編で、各約20分。ドラマは精神疾患のある母親に代わって家事と弟の世話を担う中学2年の女子生徒が主人公で、家庭と学校での姿をそれぞれ描く。
女子生徒は下校後すぐに掃除や夕飯の準備に取りかかり、不安定な母の感情のサポートや薬の管理もする。家でのケア労働が影響し、遅刻や居眠りが増える生徒。声をかけるクラスメートや、寄り添う教員など周囲の視点も添えられている。
経験者へのインタビューでは、障害のある兄弟姉妹を持つ人たちの当事者団体「栃木きょうだい会」を立ち上げた仲田海人(なかたかいと)さんや、支援団体「ケアラープロジェクト夜明け」の斎藤久美子(さいとうくみこ)さんが出演。「家に帰ってほっとすることがなかった」などと当時を振り返り、必要としていたサポートを語っている。
県こども政策課は「ヤングケアラーは珍しい存在ではなく身近にいるかもしれない。気にかけ、声をかけることから支援につなげたい」としている。
 ポストする
ポストする