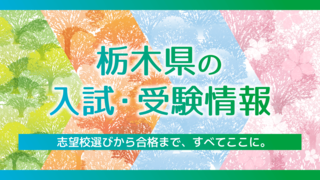栃木県と慶応大医学部は25日、卒業後に医師として県内で一定期間働く代わりに修学資金の貸与を受けられる「県地域枠」を創設すると発表した。同大医学部が地域枠を設けるのは、本県が全国初で唯一。創設の目的や制度の在り方などについて、同大医学部の金井隆典(かないたかのり)学部長に聞いた。報道陣の囲み取材での一問一答や、県との協定締結式でのあいさつは次の通り。
-地域枠を設置する意義や期待は。
「多様な人材が大学に集まることが大事だと考えている。さらに多様性のある大学に発展させるため、栃木県が手を挙げたくれた意義は大きい。県内には慶応とゆかりの深い病院がたくさんある。地域医療の充実に貢献していければ」
-どのような人材の育成を目指すのか。
「医学部は多様な人材の化学反応によって人間を大きくするということが教育の根底にある。井の中の蛙(かわず)ではなくて、さまざまな地域出身者が集まる医学部で生活する。地元に戻って地域医療を支える骨太の人材を育てるために多様性は大きなキーワードになるし、後々に海外で成功することにもつながると思う」
-県地域枠の定員は。
「恒久的な定員枠66人のうち、1人を県地域枠に充てたい。地域枠は臨時定員枠に設けるのが主流だが、われわれは恒久的な定員枠で地域医療を支えていきたい。(県地域枠は)2026年度入試から適用するつもりだ」
-選抜方法は。
「基本的には一般入試と同じ方法を考えている。詳細はこれから詰めて25年6月ごろの要項で発表する。2次試験の面接に付加する形として、県庁で面接して栃木への愛情や思い、地域医療への志のある方を選ぶことも一つのアイデアとして県側と協議している」
-義務年限は。
「先行する大学に倣って9年間とする。詳細はこれから詰めるが、特色として途中で海外留学や大学院に進学できるようなフレキシブルな制度にしたい」
-なぜ栃木県なのか。
「慶応大病院と栃木県の主要病院はつながりが強い。済生会宇都宮病院、県立がんセンター、国立病院機構栃木医療センター、足利赤十字病院、佐野厚生総合病院、那須赤十字病院などに、昔から多くの人材を派遣してきた。慶応医学部は栃木県には親近感を抱いている。働いたことがある医師が多いからだ。慶応としては、栃木県には全国でも突出した数の人材を送っていると認識している」
-地域枠を他県にも広げる考えはあるのか。
「まずは栃木でしっかり基盤を固めたい。それから他県に広げることはあり得るが、拙速に交渉することはない。まずは地に足を着けて栃木から制度をしっかりと育てていきたい」
「日本経済が厳しい中、私学の医学部に進学するのを躊躇(ちゅうちょ)する学生もいると思うが、扉を開いてくれた栃木県には感謝したい。ぜひ多くの学生が地域枠にチャレンジしてもらえたら。多様な人材が人を育てるので、さまざまな地域から学生が入学する医学部とする一つのきっかけにしたい」
-多様性を重要視しているが、入学者の傾向は。
「慶応大医学部は首都圏1都3県の学生が非常に多い。4割が付属校の進学。6割が一般入試だが、そのうちの7割が首都圏出身で、残りの3割が関西を含めた地方の出身。人材の多様性は重要だ。4月には北里柴三郎未来人材育成基金を創設し、さまざまな学生が慶応大医学部にチャレンジできる制度も作った」
◇協定締結式あいさつ
「慶応大医学部は創立100周年を迎えたが、創立時から栃木県とは非常に縁が深く、さまざまな病院で卒業生が活躍している。そんな中で高度先進医療を担う人材を安定的に栃木県で展開するための奨学制度ができたことはうれしい。全国からさまざまな人材が集まるキャンパスで県出身の学生がもまれて、故郷に戻って栃木県の医療を支えていく循環ができれば。実のある制度になるように県職員や大学職員、教員が一体となって良いプロジェクトにしていきたい」
「学生の頃から栃木県の病院に見学に行ったり、臨床実習は栃木県の病院を割り当てたりしていきたい。先行して地域枠を持つ大学とも相談していければ。6年間で栃木県の医療に携わる責任感や誇りを醸成する企画も行っていきたい」

 ポストする
ポストする