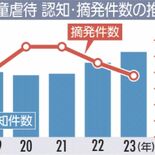12日で発生20年となる小山兄弟虐待死事件をきっかけとして、小山市内で虐待や貧困など困難を抱える子どもを支えている元県職員がいる。子どもの居場所などを運営するNPO法人「こどもの育ちを支える会さくらネット小山」の高橋弘美(たかはしひろみ)理事長(64)だ。事件当時は亡くなった兄弟の対応に当たった県南児童相談所(児相)に勤務。元職員の一人として、ぬぐえぬ後悔を抱えながら「生活課題を抱える親子が安心して暮らせる地域をつくりたい」と道筋を探り続けている。
事件発生は2004年9月。同市内の小林一斗(こばやしかずと)ちゃん=当時(4)=と隼人(はやと)ちゃん=同(3)=兄弟が同居する男から日常的に暴行を受けた末、思川に投げ込まれ、水死した。
高橋さんは当時、県南児相の児童福祉司として栃木市を担当。兄弟に関わることはなかったが、事件前に2人の一時保護を解除した同児相の判断は世間の猛烈な批判にさらされた。「取り返しの付かないこと。残ったのは消えることのない後悔」。職員の一人としてそう思い続けてきた。
事件後、児相の体制や調査権限が強化される一方で虐待リスクのある親を支える制度が充実していないと感じていた。出会ってきた親たちは、自身も被虐待児だったり貧困などの困難を抱えていたりと苦しみの中で生きていた。
「弱い親を罰するだけでは問題は解決しないのではないか」
自分にできることは何か。12年、52歳で県を退職し、同市内で要支援児童らを預かる子どもの居場所でボランティア活動をする傍ら、市スクールソーシャルワーカーなども務め、進むべき方向性を探った。
子どもの居場所「おひさま」を開所したのは16年。以来、ネグレクト(育児放棄)や貧困などで十分な養育を受けられない子どもを受け入れ、食事や入浴など生活支援をしてきた。利用者は通算で42人を数える。
時には子どもに親への弁当を持たせたり、家の掃除を手伝ったり。寄り添い、つながり続ける中で親や子が胸の内に秘めたSOSを拾い上げられる関係づくりに力を入れてきた。
20年からは子どもを宿泊させられるショートステイ事業を始め、23年には隣家に自立援助ホームも開所した。それでも「まだまだ、やり足りない」と支援の充実へ頭を悩ませる毎日だ。
20年前、幼い兄弟の命は守られなかった。「同じ悲劇を繰り返さないためには、親子が幸せに生きられる環境を整えるしかない」。事件への後悔が、今も高橋さんを突き動かしている。
 ポストする
ポストする