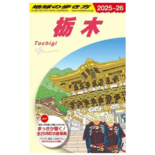【那須】現存する歴史的な土木構造物の顕彰に取り組む公益社団法人土木学会は24日、豊原甲から福島県白河市に架かるJR東日本の「黒川橋梁(きょうりょう)(上り線)」を本年度の選奨土木遺産に認定したと発表した。近代鉄道技術を伝える橋と重厚感を感じさせる石張り橋脚が連続している点が評価され、認定された。本県関係の認定は20件目。
東北本線の黒磯-白河駅間は1887年に開通した。急勾配が連続していたことから、1915年度に勾配改良工事が始まった。その一環として黒川橋梁が20年に架けられ、現在も利用されている。
黒川橋梁(上り線)は豊原-白坂駅間の黒川に架かる長さ約333メートルの橋梁。鋼ワーレントラスと呼ばれる三角形に部品を組み合わせる鉄道技術が用いられている。明治期以降に日本に伝わった、当時としては最先端の技術が使われているという。
橋を支える鉄筋コンクリート橋脚は6基あり、高さは10メートルほど。このうち2基は下部が丸みを帯び、残りの4基の下部は四角い形をしている特徴がある。またJR東日本大宮支社の図面によると、橋脚には鉄筋として古レールが使用されているといい、土木学会関東支部選奨土木遺産選考委員の福島二朗(ふくしまじろう)足利大非常勤講師(69)は「鉄筋コンクリート技術黎明(れいめい)期の大きな特徴」と解説する。
福島さんは「人里離れた場所にある点などが土木構造物らしく、橋脚は石張りでデザイン性にも優れている。長い年月をかけてこの地の地形に溶け込んだ土木構造物だ」と評価した。
選奨土木遺産は本年度、全国で14件が認定され累計531件になった。
 ポストする
ポストする