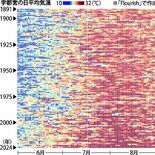テレビ局のスタジオのような場所に立つニュースキャスター風の女性の映像がスライドに映し出された。カメラが徐々に寄っていき、女性がこちらに向かってほほ笑んでいるのが分かる。女性がゆっくりと左側に歩を進めると、左右の脚が入れ替わり、ゆがんだ。AIが生成した動画だ。会場からは失笑が漏れた。
しかし記者は女性が動き始めるまで、本物の映像と見分けがつかなかった。技術の進歩に感銘を受けるとともに、本物に近いうその映像を誰もが容易に作れる現実に、少し気味の悪さを感じた。

10月3、4の両日。秋の気配を感じる曇天の宇都宮市で、全国の新聞社や放送局などが集まり意見を交わすマスコミ倫理懇談会(マス倫懇)の第66回全国大会が開かれた。
下野新聞社で編集局デジタル報道部に所属する記者は、1日目の分科会「生成AIとメディア」に参加した。
全国紙やテレビ局、出版社の担当者や専門家が実際の活用事例や課題、展望を紹介。会議室に詰めかけた記者らは持参のノートPCでメモを打ち込み、質疑応答では熱心な議論が交わされた。

記事冒頭の映像を紹介したのは関西テレビ放送の栗山和久(くりやまかずひさ)氏だ。「生成AIは映像業界の産業革命か!?」と題し、生成AI機能を搭載した映像編集ソフトや動画生成サービスが業界にもたらす影響と課題について講演した。
動画をはじめ、文章や音声の生成はAIへのプロンプト(指示)を基に行われる。生成物には誤った情報をあたかも本当のように出力する「ハルシネーション」が紛れ込むなど、さまざまなリスクが存在する。
栗山氏は「生の人と人が会い、現場で取材を行う価値が相対的に高まっている」と強調した。

同時にAIによる字幕加工など作業効率向上のメリットにも言及し、「うまく使って、現場は粘り強い調査報道などに時間を費やせるようになってほしい」と期待した。
◆ ◆
試みに、マス倫懇のルポ記事冒頭を対話型AI「チャットGPT」に出力させてみた。
指示「10月3、4日の両日、宇都宮市でマス倫懇が開催されました。生成AIをテーマにした分科会に参加した新聞記者の記事冒頭をルポ風に書いてください」
回答「会場に入ると、どこか落ち着かない空気が漂っていた。10月の晴れ渡る空の下、宇都宮市に集まったのは全国各地からの新聞記者たち。会議室には、最新の技術とメディアの未来に関心を抱く人々が詰めかけていた。テーマは『生成AI』-近年急速に進化し、報道現場にも深く入り込んできたテクノロジーだ。
(中略)
『便利なのは間違いないが、ジャーナリズムの本質をどう守るのか?』
ある記者がノートにペンを走らせる手を止め、眉をひそめた。生成AIは文章を瞬時に生成できるが、それは本当に報道に必要な『真実』を伝えられるのか。多くの参加者がこの問いに対して自分なりの答えを探していた」
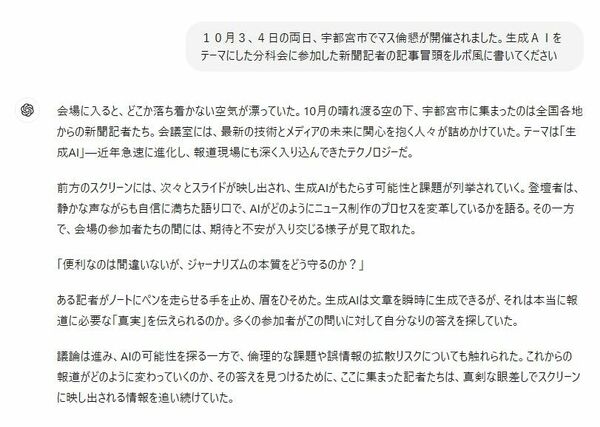
◆ ◆
ここまで読んでくれたあなたは回答に潜むいくつのハルシネーションに気付いただろうか。
気象庁のデータによると宇都宮は3日、終日曇りか雨だった。また参加者は新聞記者に限らず、「ノートにペンを走らせる手を止め、眉をひそめた」記者の存在も確認できていない。
そもそも過去に学習した文章のパターンによって出力されている点で、全てがハルシネーションと言っても差し支えないだろう。
現場に足を運び、正確な情報を伝える報道の仕事は今後ますます重要になる。気持ちを引き締められた1日となった。

 ポストする
ポストする