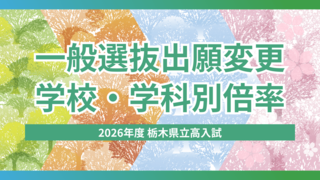第50回衆院選は27日、投開票日を迎える。自民党派閥の裏金事件を発端とした政治改革や物価高対策、安全保障政策などを巡り、各党・各候補者が激しい論戦を繰り広げている。政権選択と位置づけられる3年ぶりの総選挙である。自民、公明両党による連立政権の継続か否か。有権者は1票を投じることではっきりと民意を示す時だ。
今回の選挙は小選挙区と比例代表の計465議席に9党などから1344人が立候補し、このうち女性候補数は314人で過去最多となった。本県は五つの小選挙区に、女性2人を含め前回より4人多い16人が立候補し、政策を競い合い支持を求めている。
「政治とカネ」は最大の焦点だろう。石破茂(いしばしげる)首相(自民党総裁)は公示後の第一声で裏金事件に触れ「深い反省の下、もう一度、新しい日本をつくる」などと訴えた。選挙戦を通じ、信頼される政治についてどれほど説明責任を尽くしたのかが厳しく問われよう。
物価高を巡る経済対策も主要な争点である。県が先日発表した2024年度の県政世論調査でも、直近5、6年の暮らし向きに「悪くなった」と答えた県民は回答者全体の51%に上った。個人消費が振るわないのは、物価高をしのぐ所得を家計が得られていないからだ。各党の政策について、将来世代へツケを回さないという観点を含め冷静に見極めることが肝要である。
ロシアのウクライナ侵攻が続き、中東の戦火もやまず、世界の対立と分断は一段と進行する。国内では、人口減少と少子高齢化が加速している。社会の活力を失わずに、持続可能な社会保障制度を構築していかなければならない。
安全保障環境の悪化から防衛力の抜本的な強化も進み、防衛費の大幅増の財源には増税も予定される。異常気象など地球温暖化の影響をいかに抑制していくのかは、切実かつ深刻な問題である。
こうした山積する難題のかじ取りを委ねる候補者や政党には、正義、透明性、寛容さを求めたい。激しい言葉が飛び交う交流サイト(SNS)などが招く社会の分断を抑え、包摂的な社会をつくるには、特に政治が寛容さを示さなければならない。この三つの要素を大切にする候補者や政党をまず優先して探したい。
一方、今回の衆院選で野党の選挙協力は進まず、主要4野党のいずれかの候補が自公与党と一騎打ちになるのは、289小選挙区のうち本県2区を含む52選挙区にとどまる。野党共闘が進んだ21年の前回衆院選に比べ、選挙後の政権枠組みは明確に示されていない。
気がかりなのは投票率である。衆院選は国の針路を左右する重要な国政選挙だが、投票率は12年以降、50%台が続き、若年層の低さが目立つ。県内は過去2回微増したものの、いずれも50%台前半だった。ほぼ半数が棄権している現状は、民主主義が健全に機能しているとは言い難い。
政治に失望するのではなく、期待できる政治を託せる候補者や政党をじっくり吟味して選び、1票の力を信じて投票する。特に若者へ呼びかけたい。沈黙するのはもったいない。社会保障や安全保障制度の在り方は、自身の将来にもかかわる。未来を選択する権利を行使しよう。
 ポストする
ポストする