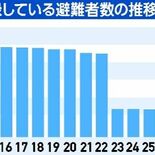東日本大震災に伴う東京電力福島第1原発事故の発生から11日で14年となった。溶融核燃料(デブリ)の試験的な取り出しが2024年秋に行われ、国と東電が目指す51年までの廃炉作業は3段階ある工程の最終段階に進んでいる。進捗(しんちょく)を確かめるため、下野新聞社の取材班は1月上旬、原発構内に入った。デブリ取り出しに廃棄物対策、汚染水処理-。取材を通じて見えたのは、廃炉への長く険しい道のりと、山積する課題に絶えず向き合う多くの作業員の姿だった。現場の今と、再生に向け歩む地域の様子を報告する。

1月10日午前9時過ぎ。10カ所あるゲートで入構手続きに入った。身分確認や金属探知などまるで空港の出入国審査場のような雰囲気の中、手こずる記者を尻目に作業員らが絶えず出入りする。作業着姿の男性に交じり女性の姿もある。その数、1日約4500人。24時間体制で廃炉に向かい作業が続いていることを実感する。
入構し、バスで移動していると、まず鉄骨むき出しの1号機が目に入った。展望台に立つと、放射性物質の飛散を防ぐため、建屋全体への大型カバー設置工事が行われていた。水素爆発が起きた事故当時のままの部分もあるが、今夏その姿は全て覆われ、見えなくなるという。
残り:約 2621文字/全文:3195文字
下野新聞デジタルに会員登録すると…
- 事件事故や高校野球・イベントなど速報でとちぎの「今」が分かる
さらにスタンダードプランなら…
- デジタル有料記事の大半が読める
- 教育や仕事に役立つ情報が充実
愛読者・フルプランなら…
- アプリも使えて、おくやみ情報もいち早く
 ポストする
ポストする