「ふーん、慶成出てるのか。なかなかの才女だな」
奨吾(しょうご)は画面に表示された応募者のプロフィールを眺めた。慶成大学は都内でも有数の私立大学だ。そこの経済学部経営学科を卒業していた。名前は紺野麻理亜(こんのまりあ)。女優のような名前だと奨吾は思った。
「おい、これを見ろ」
奨吾は画面の一点を指でさす。彼女の経歴の欄だ。一昨年の四月に株式会社ヘラクレス・コンサルティングに入社したが、今年の三月に「一身上の都合により退職」とあった。現在はサービス業に従事しているとのことだ。
「ヘラクレス・コンサルティング? 有名なんですか?」
「有名なんてもんじゃないよ。日本でも一、二を争う外資系のコンサルだ。入社するだけでも優秀な証だよ」
「そうなんですか。でも二年で退社しちゃうなんてもったいないですね」
「まあな」
奨吾は腕を組み、紺野麻理亜なる女性のプロフィールが表示された画面を見る。見れば見るほど適任に思えてならない。東京在住の二十代女性。慶成大卒でヘラクレスでの二年間の勤務経験あり。彼女こそが天が遣わした勝利の女神ではないか。いや、そこまで考えるのは気が早いか。
「おい、この子のことをフォローするぞ。何としても堅魚(かつお)市を気に入ってもらおう。この子は必要な人材かもしれん」
「でもどうやって?」
「決まってるだろ。おもてなしだ」
※
目の前には大量の刺身が並んでいる。いわゆる舟盛りというやつだ。見るからに新鮮そうで、東京のスーパーで見かけるものとは大違いだ。麻理亜は迷った末、一番美味しそうなカツオのタタキに手を伸ばした。やはり高知に来たならカツオを食べねばなるまい。
「おお、やっぱりカツオですね。お目が高い」
目の前に座る男性が手を叩(たた)く。その隣にも中年のおじさんが座っている。
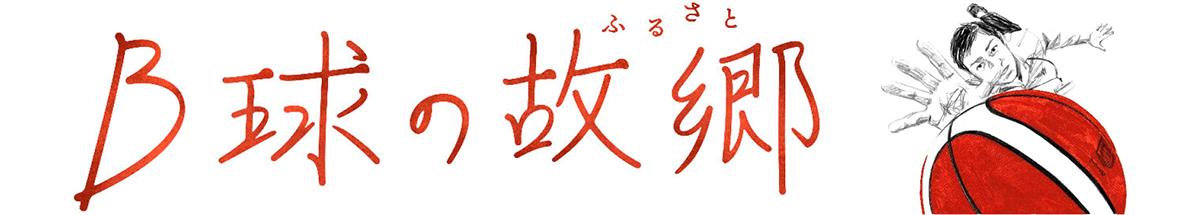
 ポストする
ポストする



















