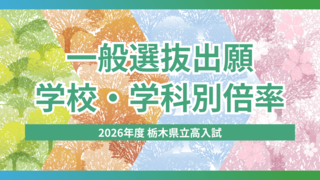戦史の継承が途絶えてもおかしくない状況だった。1945(昭和20)年2月、野木町の上空で日本軍機で米軍爆撃機B29にぶつかり、軍人倉井利三(くらいとしぞう)少尉が命を落とした。空戦の様子や殉死を伝える碑を紹介する企画「少尉のいしぶみ~野木の空戦~」を1月、3回に渡って連載した。
野木の空戦-。宇都宮空襲や宇都宮市内に駐留した陸軍第14師団といった戦史とは異なり、資料は乏しく、取材は難航した。
倉井少尉の碑は、野木町佐川野の畑の端にひっそりと建つ。案内板は無い。
関係者を数珠つなぎで探り、畑の所有者の農業柿沼誠(かきぬままこと)さん(68)に出会った。「どんな風に書くんだい」「もう昔のことでしょうが」。予想に反し、柿沼さんの言葉の熱量が低く感じられた。
倉井少尉の碑は、機体が墜落した畑に柿沼さんの祖父が建て、父が受け継いだ。祖父や父が鬼籍に入った今、柿沼さんが伝え聞いた記憶が唯一の頼りだった。
宇都宮から車で1時間超。何度も野木に通ううち、柿沼さんから、いろいろな話が聞けるようになってきた。「おやじが言ってたことを思い出しておいた。妹や弟、近所の年寄りとかにも聞いて回ったよ」。取材には私を含め3人で取りかかったが、記者たちの熱に当てられたのか、いつの間にか柿沼さんは“4人目の記者”になっていた。
記事の掲載後、柿沼さんは近くの小学校から依頼を受け、子どもたちに野木の空戦や平和の尊さを語る講師を務めた。
現在は独自に野木の空戦をまとめ、冊子も作っている。「冊子を野木町の図書館に置いてもらえれば、後世にも残るでしょう」。熱っぽく語る柿沼さんの言葉を聞き、戦史の継承を少しだけ後押しできた気がした。
(報道部 枛木澤良太)
太平洋戦争の終結から80年の節目を迎えた今年、下野新聞社はさまざまな平和報道を展開している。戦争体験者がわずかとなり、記憶を伝えることが年々難しくなる中、平和への願いを未来へどう継承していくか。15日に始まる新聞週間に合わせ、取材を担当した記者が抱いた思いを紹介する。

 ポストする
ポストする