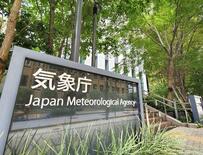水路を覆い尽くすように、緑の植物が広がる-。宇都宮市の水路で見つかった植物の正体は、水槽用や観賞用としても広く流通している外来水草の「アマゾントチカガミ」だ。南米原産で繁殖力が強く、広がれば生態系に影響し、農業被害を引き起こす懸念もある。
栃木県内では同市瓦谷町の水路で初めて確認され、11日には県が駆除活動を実施。市民ボランティア34人も参加して、作業が行われた。


「こんなに広範囲に広がっているとは…」。午前9時、胴長に着替えた参加者たちが水路を見渡し、驚きの声を漏らした。幅2メートル、約400メートルにわたり、水面にアマゾントチカガミが繁茂していた。
この日は200メートル区間で駆除を実施。水路に入った参加者たちは黙々と手や網で水草をかき集め、袋に入れていった。「水で重くなっているので見た目以上に重労働です」と、参加者の男性は汗をぬぐった。
約2時間後、覆われていた水面があらわになり、見違える光景に。「緑のじゅうたんが、やっと水路になった」と感嘆の声も。宇都宮市在住の会社員、吉田浩昭(よしだひろあき)さん(37)は「環境保全に協力できて良かった」と晴れやかな表情を見せた。

その後も県職員が水中に残った根や葉を取り除き、フレコンバッグ25個分のアマゾントチカガミを回収。クレーンで水路から引き上げた。県自然環境課の担当者は「初めての試みだったが、たくさんの方の協力のおかげで予想以上にきれいにできた」と話した。
アマゾントチカガミの繁殖場所の近くには、国の準絶滅危惧種の水草・ナガエミクリが生育している。県立博物館の星直斗(ほしなおと)自然課長は「アマゾントチカガミの繁殖を食い止めなければ、ナガエミクリが追いやられてしまう可能性がある」と指摘した。

県は年度内に残りの区間でも駆除活動を行う予定。一度に完全に取り去ることは難しいため、来年度も監視と駆除活動を続ける方針という。

 ポストする
ポストする