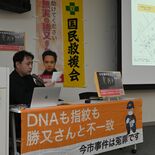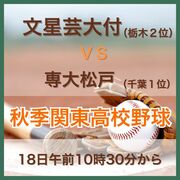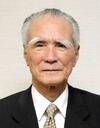「ランドセルの代わりに、黄色のリュックサックが定着している地域がある」。西日本新聞「あなたの特命取材班」が、高価なランドセルが広く使われている理由を調べていると、こんな情報が寄せられた。そこは福岡県みやこ町。なんと普及したのは少なくとも半世紀前からという。その謎を探るべく、記者が現地に向かった。
同町勝山地区の黒田小を訪れて驚いた。集団下校する児童が背負っていたのは、黄色のリュックだった。
馬場育実校長によると、全校児童176人のうち約8割がリュックを使用している。使っているのは、町内でも同地区の久保小、諫山小のみという。
黒田小では毎年1月ごろ、入学予定者に行う説明会でリュックを紹介。希望者は購入するが、ランドセルなど他のかばんの使用も問題ない。馬場校長は「『経済的に助かる』という声が多い。荷物が増える高学年の子も『軽い』と言ってくれる」と説明してくれた。
保護者の声から
高価で重い-。ランドセルを巡る課題は50年以上前から変わらないようだ。
このリュックを製造・販売するのが学生用品メーカー「マルヤス」(京都府向日市)。商品名は「ランリック」と呼ばれ、誕生は1968年にさかのぼる。
その頃、高価な牛革製を買えない家庭は、豚革製のランドセルを購入していたという。「ブタ、ブタといじめられ、子どもが学校に行きたがらない」。保護者からそんな声を聞いた小学校の校長が、同社に相談したのがきっかけだった。
ナイロン製で重さ約300グラム、値段は当時の590円ほど。体に負担がかからない軽さで安価を目標に1年で開発。交通事故防止のため黄色にした。
その後も改良を続け、色や種類も増やした。現在は教科書やタブレット端末など荷物の増加に伴い、重さは2倍強に。原料高騰の中、主力商品は1万円台前半の価格帯に抑える。口コミで近畿圏を中心に広がり、累計の利用校は約340校。ピーク時には年間2万個を販売した。
地域の誇りに
同社によると、九州で唯一このリュックを使っているのが、みやこ町のようだ。町に聞くと「導入の経緯は今は分からない…」というが、独自に調べている人に巡り合えた。
「50年ほど前には使われていた」と説明するのが、町歴史民俗博物館の学芸員、井上信隆さん(49)。井上さんによると当時、ランドセルを購入できる家庭とできない家庭があり、「同じ物を使ってもらおう」と導入されたようだ。
井上さんも小学生時代に愛用した。「遠足にも使った。大人になり、よそでは使っていないと知って実は驚いたんです」と笑う。
人知れず勝山地区で愛用されてきたこのリュック。井上さんは誇らしげに語った。「平等な教育環境を整えるという当時の先生たちの熱意が、リュックに詰まっているような気がします」
(西日本新聞)

 ポストする
ポストする