世界に誇る日本のイチゴの生産をけん引する本県と、その背中に迫る福岡県。二大産地を中心に、国内のイチゴ市場は群雄割拠の時代に突入している。栽培面積は右肩下がりでも、産出額は伸びている。世帯の消費量は減っているのに、購入金額は増えている。そんな日本のイチゴ事情について、下野新聞社は西日本新聞社(福岡市)と共同取材を実施。東西の市場関係者2人に解説してもらった。
◆文孝商店(東京都大田区)社長 星野和一さん(72)

-仲卸としてイチゴを専門に取り扱っていますね。
「皮をむかなくて食べられるのがいい。見た目もいいし、香りがある。赤い色は目に麗しく、どんな料理でも演出できる」
-栃木、福岡両産地のイチゴをどう評価している。
「今の日本のイチゴで代表的なのは、東の横綱が栃木県、西は福岡県だ。とちおとめは大衆的で、生食用はもちろん、酸味と甘みがマッチするのでケーキに合う。シーズンを通して食味が安定しており、実が比較的硬く、日持ちもしやすい。優れた要素を持っており、これを越す品種を作るのは難しい」
「対してあまおうは高級感がある。市場では他品種とあまり変わらないが、専門店ではより高値で売られている。結婚披露宴のケーキなど、話題になる場面ではよく使われる印象。丸みがあって色つやがあり、実が軟らかいのが特徴だ」
-とちおとめに代わる品種として、本県オリジナルのとちあいかが誕生した。
「とちあいかは実の中が白い。甘く香りも高いし、追熟しやすく色が回りやすい。将来的にとちおとめを上回ることができる品種だ。一部、品質に課題はあるが、作り慣れるとクリアできると思う。とちおとめもそうやってクリアしてきた。とちおとめの優れた要素を受け継いでもらえれば、と期待している」
「一つ欠点を挙げるとすると、酸味がないこと。今までは、酸味がないイチゴはケーキに合わないという考え方が主流だった。断面も赤い方が映える。パティシエが考え方を変えてくれるといいが」

-あまおうの後継品種も注目される。
「あまおうも今後、後継が出てくるのだろう。福岡は新しい品種ができると、生産者全員がその品種に統一して栽培する。だが、例えば『輸送にいいから』と硬いものにしようとしても、消費者に『軟らかいものが好き』と言われればそこまでだ。後は消費者の好みの問題だと思う」
-イチゴは季節によって出荷量に差があるのが課題とされる。
「(夏秋なども収穫できる)四季成(しきなり)品種を作るのは本当に難しい。単価が高くないと割に合わない。だが理想は一年中売れること。うちは業務用なので、半年は国産、半年は米国などの海外産を使っている」
-全国的にはイチゴの品種の数が増えている。
「昭和のころはせいぜい8種類ぐらいだったが、平成になって暮らしや考え方が豊かになり、新たに品種を作る産地が多くなった。今は東京・大田市場だけで20種類はあるだろう」
「お客さんが自分好みのイチゴを選べる時代に入ってきたと捉えられる。『今日は何を食べよう』と選択できるように、イチゴの品種も豊富になってきている。どの品種も色つや、形、食感が違う。一つ一つ魅力があるし、そういう違いは消費者の気持ちを豊かにする」
-イチゴの輸出についてはどのように考える。
「特に輸出に力を入れているあまおうは、輸出先の香港やシンガポールなどが高級志向で高く売れる。立地も福岡県から近く、輸送時間も短い。栃木県も輸出に力を入れてきている。日本のイチゴは海外から見れば芸術品で高く売れるから、輸出という考え方はいいと思う」
「ただ、国内にもイチゴを食べない人がまだいる。イチゴが嫌いな人は老若男女いない。国内でもっとイチゴを食べてほしいと思っている」
◆大果大阪青果(大阪市)果実部副部長 槻並靖英さん(52)

-近年のイチゴの市場動向を教えてください。
「イチゴは他の果物が少ない冬場に入荷するので売り場で重宝されやすい。子どもからお年寄りまで幅広く支持され、ここ数年、コロナ禍の巣ごもり需要で果物全般(の売り上げ)が伸びていたが、夏ごろから下降の傾向が見られる。コロナが落ち着いてきて、消費者の関心が外食や旅行に向いてきたのに加え、さまざまな物が値上がりした影響で嗜好(しこう)品の果物が節約の対象になっているとみている」
-関西圏でのイチゴの取り扱い状況は。
「大果大阪青果での取扱金額は6割強が九州産で、関東産はほとんどない。スーパーなどでは『あまおう』と『その他イチゴ』という取り扱いで、あまおうのみが別のランクで売られている。今は九州の上位4県(福岡、熊本、長崎、佐賀県)が異なる品種を栽培している。スーパーが大型化しており、一品種だけで特売に必要な量を確保するのが難しくなっている」
-あまおうは別格なんですね。
「(本格販売開始から)20年たってもブランドを維持できている。最も懸念しているのは生産者や生産面積の減少だ。収量がさらに上がって、生産者が利益を確保しやすいものができればいい。あまおうは品種名ではなく商標。商標を生かしながら、新たな品種を展開するのもいい。特に問題はないが、ぜいたくを言えば、(生産面で)もう少しいい品種を期待したい」
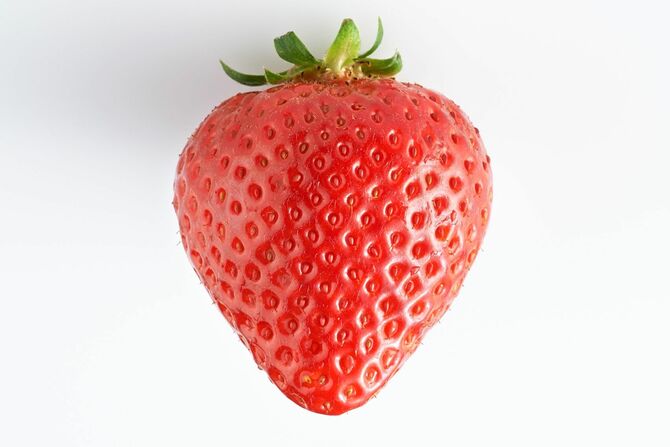
-栃木県産を関西で浸透させるために必要なことは。
「全国的にイチゴの栽培面積が減っている中、日本一の産地の取り扱いを増やしたいと動いてきた。だが食味の問題ではなく、関西圏の市場では今まで主に九州各県がしのぎを削ってきたので、新規はなかなか浸透しなかった。浸透させるためには、安定的に関西へ出荷しないと難しい」
-本県の新品種とちあいかの評価は。
「食味が良く、大玉で形もいい。関西圏でも広がる可能性はある。ただブランド力がまだない。関西での地盤をつくりながら、徐々に売っていきたいと慎重に進めているところだ」

 ポストする
ポストする















