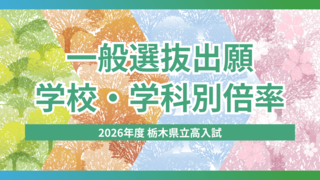【栃木】西方町元の福正(ふくしょう)寺は、本年度に創立150周年を迎える西方小が同寺で発祥したことを示す石碑を境内に建立し4日、お披露目した。江戸時代から寺子屋教育に力を入れていた同寺は、明治時代初期に100人超が学び、1873年に同校の前身「日新学舎(にっしんがくしゃ)」として開校した。西方地域の庶民教育の礎を担っていた歴史を後世に残そうと、松涛淳一(まつなみじゅんいち)住職(67)が約20年前から記録を調べていた。
松涛住職によると、福正寺は1278年、鎌倉時代の僧一向上人(いっこうしょうにん)により開かれた。江戸時代の天保年間は13人の僧が在籍し、関流和算の最高免許を授けられた弁誉朝阿上人(べんよちょうあしょうにん)の下、寺子屋教育に熱心に取り組んだ。
幕末に衰退したものの、明治を迎えて地元の塾「中澤(なかざわ)塾」が同寺へ移転され、100人を超える子どもが学んだ。学制発布を受けて1873年8月、同寺に日新学舎が開校。同年12月には約400メートル東の現西方小の地に移った。
松涛住職は約20年前に地元住民から当時の経緯を記した資料を受け取り、調査していた。「どこかで形に残さないとうずもれてしまう。この寺が庶民教育の場だったことを知らしめたかった」と振り返る。同校創立150年の節目に合わせ、石碑の建立を決めた。
石碑は高さ約150センチ、幅約60センチ。松涛住職が「西方小学校発祥之地」と揮毫(きごう)した。傍らには西方小創立までの歴史を記し、二宮金次郎(にのみやきんじろう)像も建立した。
4日には清めの儀式「洒浄(しゃじょう)式」が行われ、参列した約20人の檀家(だんか)らが建立を祝った。松涛住職は「150年の区切りで披露できてよかった。先人の建学精神を末永く伝えていきたい」と語った。
 ポストする
ポストする