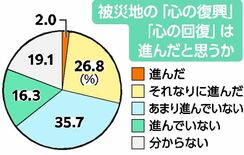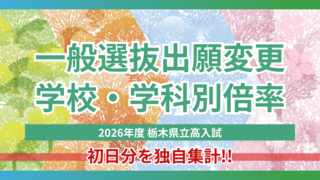農耕用のトラクターは公道を走っていいの?-。福井新聞の調査報道「ふくい特報班」(通称・ふく特)に疑問の声が寄せられた。関係機関に取材すると、運転免許をはじめ一定の条件を満たせば走行できるようだ。ただ、農業者からは「周囲の目が厳しい」「肩身が狭い」といった嘆き節が聞こえてくる。
投稿者は、ふく特のLINE(ライン)に、福井市内の橋を走行するトラクターの写真を添付し「渋滞を起こしています。トラクターが公道を走っていいのでしょうか」とつづった。
農耕用トラクターについて国土交通省福井運輸支局に尋ねると、道路運送車両法では寸法や最高速度などにより小型特殊自動車(小特)、大型特殊自動車(大特)に大別される。大特の申請先は運輸支局で、担当者は「通行許可を得るか、ナンバープレートがないと原則として公道を走れません」。
大特と小特で違い
大特は車両の持ち込み検査でブレーキやランプなどの保安基準に適合していれば、ナンバープレートが発行される。自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入する必要があり、基本的に2年ごとの車検もある。保安基準を満たしていないと整備命令の対象になり、従わなければ罰則がある。
小特の申請先は市区町村で、自賠責の加入対象ではない。トラクターを取得したら書類を提出し、ナンバープレートの交付を受ける。福井市によると毎年2千円の軽自動車税がかかり、不申告だと条例違反で10万円以下の過料が科される恐れがある。市民税課は「小特のナンバーは課税の証し。保安基準を満たす証明ではない」とし、道路走行の有無を問わず車両所有の“前提”だと説明する。
道交法では運転免許が重要な条件だ。県警交通指導課によると、小特は小型特殊免許または普通免許など、大特は大型特殊免許が必要。公道や農道にかかわらず不特定多数が出入りする道路で、所定の免許がないと無免許運転になる可能性がある。
農繁期にはトラクターの走行に関する問い合わせが各署に寄せられるという。県内では昨年、トラクターが農道から転落した死亡事故も発生。同課の担当者は「免許や保安基準などの条件を満たしていなければ指導や取り締まりの対象になり得る」と注意を促す。
作業機装着の条件緩和
法令が複雑に絡む中、農林水産省などによると、2020年の道路運送車両法の運用見直しで、代かきなどの作業機を装着したトラクターでも一定の条件を満たせば道路を走行できるようになった。
農業者に実情を聞いてみた。県内13経営体で構成し農産物や農作業の安全性を示す認証「GAP」(農業生産工程管理)を取得している団体「FGA」の安実正嗣会長(74)=福井市=は「法令順守や事故防止はもちろん、周辺に迷惑をかけない配慮も不可欠な時代になった」と話す。FGAでは泥を除去する器具を載せ、農道に泥を残さないよう徹底しているという。
同市内でトラクターに乗って作業していた別の70代男性は「離れた田んぼに移動する際はトラックに載せるけど、近場だと道路を通るときもある」。地元の集落でも苦情を受けることがあり「田んぼばかりだった集落に宅地が増え、周りの目は厳しい。農家が減る中で昔より肩身が狭くなった」と寂しげに語った。(福井新聞)

 ポストする
ポストする