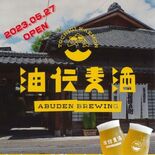栃木市といえば蔵の街。旧日光例幣使街道や巴波(うずま)川沿いには黒塗りの見世蔵や白壁の土蔵が残り、小江戸の風情を感じさせる。
日本ナショナルトラストが2005年度に実施した調査によると、中心部の17町には伝統的建造物が792棟確認され、3分の1は江戸末期-明治期の建設だった。土蔵、見世蔵などの蔵造りは254棟あった。
街の端緒は戦国武将皆川広照(みながわひろてる)が整備した城下町にさかのぼる。江戸時代に例幣使街道の宿場町として街並みが形成され、巴波川の舟運で栄えた。戦時中の大規模な空襲は免れたが、1963年度には大通りにアーケードが設置されるなど景観は重視されていなかった。
転機は88年に県のまちづくり事業に指定されたことだ。90年から大通りのアーケード撤去、電線地中化が始まり、市は建造物の外観を整える修景に着手。蔵の街という言葉も広まった。
「観光客から『落ち着く街ですね』と言われるようになった」。35年間市内のガイドを続ける市観光ボランティア協会の清田照子(きよたてるこ)会長(72)が振り返る。
市はこれまで約3億5千万円をかけて130棟の修景を補助した。2012年には嘉右衛門(かうえもん)町が国重要伝統的建造物群保存地区に選定され、街並みの維持が図られている。
だが所有者の高齢化で管理が困難になった蔵は、くしの歯が欠けるように姿を消している。市の調査で16年に確認された中心部の戦前建築物は1593棟。20年間で46%減少した。
「栃木の蔵は江戸時代から商売を続けているのが魅力。蔵が建った時代の雰囲気や1棟ずつ異なる造りをもっと伝えたい」と清田会長。厳しい現実に直面しつつも、独自の資源を残し、生かすための模索が続く。

 ポストする
ポストする