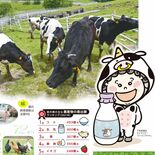生乳産出額全国第2位を誇る那須塩原市。その歴史は明治の那須野ケ原開拓とともに始まった。
那須野ケ原は、明治政府の殖産興業政策として開拓が進められた。1878年、初代県令の鍋島幹(なべしまみき)によって県営那須牧場が開設されたほか、開拓をけん引した農場「那須開墾社」が、創業翌年の81年に牛乳の生産、販売を開始した記録が残されている。1901年には大山巌(おおやまいわお)元帥の大山農場などが発足した。
酪農が盛んになったのは戦後の開拓による。当初は畑作が中心だったものの、火山灰土が作物の生育に適さなかったことや、冷害の影響で順調に進まなかったことから、冷涼地に適した酪農に転換していった。
1959年、学校給食に牛乳を提供することが法制化され、牛乳の需要が急増。市(当時の西那須野町など)は首都圏に近く、この需要に対応できた。市が全国有数の生乳生産地にまで成長したのは、この地理的な要因が大きい。
昭和40年代には、それまで手作業だった搾乳作業の機械化が進み、大型トラクターにより飼料作物の生産性も向上。これにより乳牛の飼育頭数が急増した。
昨年2月1日現在、市内では約240の農場で約2万6千頭の乳牛が飼育されている。市は「牛乳で乾杯条例」や、「ぎゅう(9)にゅう(2)」の語呂合わせから9月2日と定めた「市牛乳の日」の制定などを通し、酪農のPRに力を注いでいる。
「酪農家がこれからも市で酪農に継続的に取り組める環境整備に力を入れたい」と市農務畜産課の室井敬弘(むろいよしひろ)畜産振興係長(43)。酪農家と行政の努力が一体となり、酪農王国は今後も発展を続けていく。

 ポストする
ポストする