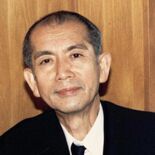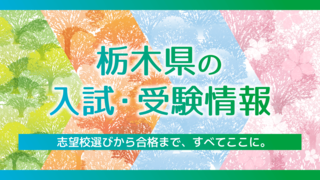宇都宮市の農業は鬼怒川、田川、姿川流域でのコメ作りを軸に発展してきた。市西部、東部の畑作地帯と共に、高度経済成長を迎えた1950年代以降、多様な農作物を東京圏に供給している。市ブランド農産物のナシやトマトは、この時期から生産出荷量が飛躍的に伸びた。
県内1位の作付面積を誇るナシは明治中期に平石地区で始まった。55年に市なし生産出荷協同組合が設立され、生産拡大の源流となった。現在は県内の作付面積の3割を占め、清原、城山地区が中心地だ。
トマトも現在、作付面積が県内1位。多様な栽培法により年間を通じた出荷体制が築かれている。主要生産地となった清原地区では55年から夏秋トマトの栽培が始まり、その後に急拡大。同時期に国本地区などでも生産組合が結成され、市内に広がった。
イチゴは52年、足利市とともに、複数の農家が連携した集団栽培の先駆けとなり、70年に露地からハウス栽培へ転換。イチゴ王国の本県を長年支えてきた。
トマトやイチゴの生産に欠かせないビニールハウス。その全国的な先駆者が石井町の小島重定(こじましげさだ)氏=2002年に99歳で他界=だ。1952年に県内で初めてハウスを導入。油紙で作ったトンネルで作物を保温し早期出荷する栽培法から、トマトやキュウリの施設園芸にまで技術が発展する一翼を担った。
一方で農家数は減少が続く。70年の8658戸から2020年には4427戸へと半減。少子高齢化の進展でさらに減少が見込まれ、農地の集約や担い手の確保が求められている。小島氏の孫で元JAうつのみや組合長の俊一(しゅんいち)さん(73)は「農業者が増える環境づくりが必要だ。若い世代には自信を持ってやってほしい」と願う。

 ポストする
ポストする