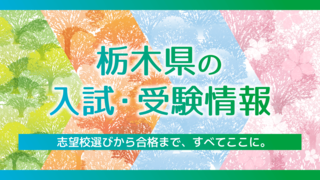「木工のまち鹿沼」を象徴する鹿沼木工団地。開設から約60年が経過した現在も存在感を放っている。
鹿沼は豊かな森林資源により、戦前から木材産業が主要産業と位置付けられてきた。戦後の復興に伴う木材需要の増加に合わせ、特に建具を中心に発展。1949年に商工省(現経済産業省)から「重要木工集団地」の指定を受け、高度成長期の住宅需要なども相まって順調に成長した。
61年の国の工場等集団化制度導入を受け、翌62年7月に組合員60人、出資金800万円で鹿沼木材工業団地協同組合が発足。鹿沼市茂呂に約32ヘクタールの木工団地が整備され、64~66年度の3カ年で計32社が進出した。
元組合役員で創生期を知る福井辰次(ふくいたつじ)さん(95)は「当時は建具の需要が著しく伸びていて、団地に人や車の出入りも多く活気がありましたね」と懐かしむ。
84年に名称を現在の「鹿沼木工団地協同組合」に変更。バブル崩壊後に加盟企業の破綻が相次ぎ組合存続が危ぶまれる事態を迎えたものの、現在は組合員、準組合員各26社で構成。建具や家具製造、建材業などに加え、木工関連以外の企業も進出するなど多様性のある団地に変化している。
団地内で毎年6月に開かれる鹿沼木工団地まつり青空市は開催46回を数え、人気イベントとして定着。昨年1月には企業主導型のかぬま木工団地保育園を開設するなど加盟社社員や地域貢献にも寄与している。
同7月の組合設立60周年の記念式典では、白石修務(しらいしおさむ)理事長が「100周年を目指せるよう一丸となって努力したい」とあいさつした。伝統を守りつつ変化も加え、組合員中心に新たな歴史を紡いでいく。

 ポストする
ポストする