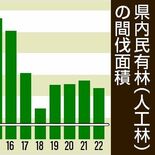全国で高病原性鳥インフルエンザが発生し始めたことを受け、栃木県内の養鶏場や公園など関係者が警戒を強めている。今季は11月下旬、佐賀県の養鶏場で初確認された。その後、鹿児島のほか隣県の茨城や埼玉でも発生した。昨季は26道県の養鶏場などで過去最多の84件が発生。本県では確認されなかったが、今季も各地で相次ぎ始め、関係者は「やるべきことをやるしかない」と話す。引き続き、農場の消毒やウイルスを媒介する野鳥の飛来防止などの対策を進めている。
「今年もこの時季が来たか」。矢板市上伊佐野の養鶏場「ワタナベファーム」代表の渡辺茂(わたなべしげる)さん(41)は、鳥インフルが大流行した昨季を思い返す。飼養するための鶏の流通が途絶え、今年夏ごろまで飼養羽数の制限を強いられた。
飼料や鶏の価格高騰が経営を圧迫。鳥インフルが発生すれば、養鶏場は危機に陥る。渡辺さんは県家畜保健衛生所とやりとりを重ね、消毒や消石灰の散布などの防疫作業を進めている。「感染予防には年中気を付けている。やるべきことをやっていくしかない」
野鳥が養鶏場に近づくのを防ぐため、県は昨年に続き、鳥が集まりやすい水場の対策を強化している。養鶏場の半径1キロ以内にある農業用ため池など計52カ所(6日時点)で、管理者や市町の協力を得て水を抜いたり、鳥よけの「防鳥たこ」を設置したりした。
本県で昨季、発生がなかったことを県畜産振興課の担当者は「水場の対策に一定の効果があった」とみる。県は野鳥を素手で触るといった過度の接触や餌付けの自粛を呼びかけている。
県養鶏協会は年内と年明けの計2回、会員農家に消石灰を配布する予定だ。大室憲一(おおむろけんいち)会長(49)は、企業が鶏卵の供給不足を懸念し、需要が落ち込むのではと危惧する。「卵余り」の傾向にあるとし、「(一般家庭など)消費者に卵を買ってほしい」と求めた。
カモ類などが飛来する井頭公園(真岡市)も注意喚起のポスターを掲示している。日本野鳥の会会員の調査によると、同公園内の池の野鳥が1カ月前から5割ほど増え、渡り鳥の飛来が本格化している。同公園の担当者は「観察に来る愛好家の方も増えてきた。ルールを守って楽しんでほしい」と話している。
 ポストする
ポストする