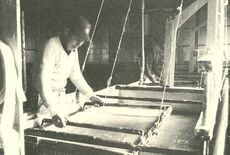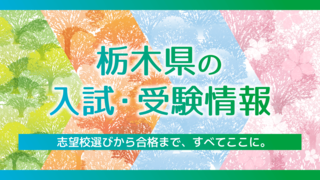矢板市、塩谷町は共に総面積の約6割を森林が占める。両市町に広がる高原山ろくは戦後、木材需要のブームに乗ってスギ、ヒノキの造林が盛んになった。旧塩原町(那須塩原市)を含む山ろく南東部は新興の高原林業地として発展した。
戦前まで広葉樹の薪炭林が中心だった一帯はスギなどへ転換されていく。造林は1960年代にピークを迎え、矢板市塩田ではスギなどの用材林が8割以上になった。同市倉掛の林業家は早くまっすぐ成長する品種「倉掛3号」を開発。小規模森林経営の道筋を照らすと注目された。
緩斜面の多い同林業地は木材の搬出がしやすく、近くに市場や製材業が集まった。同市内に58年、矢板木材共販所が開設、75年ごろの製材工場は矢板市37軒、塩谷町は24軒を数えた。たかはら森林組合の高瀬洋之(たかせひろゆき)特別対策室長(63)は「立地条件の良さが発展した一番の要因」と話す。
スギの割合が多い矢板市に対し、塩谷町はヒノキの適地も広がる。北限に近く、年輪の目が詰まっていて良質とされる。山林を有する同組合前代表理事副組合長の手塚礼知(てつかのりとも)さん(83)=船生=は「子どもの頃、父から地元のヒノキは『野州ヒノキ』として評価が高いと聞いていた」と語る。
県矢板森林管理事務所によると両市町の製材会社はここ20年、新技術を導入し、大規模企業が集中する地域になったという。
造林した森林が利用期を迎えたこともあって両市町と旧塩原、喜連川町産を扱う矢板木材共販所の取扱量は漸増傾向で、2022年は約4万1300立方メートルと過去2番目の量である。このうち矢板市、塩谷町産が約8割を占める。

 ポストする
ポストする