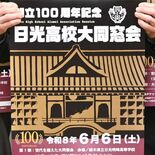黄、茶、灰、黒。モダンな幾何学模様が木箱の表面を彩る。着色ではない。自然の木が持つ色合いを生かし、組み合わせてデザインする「木彩(もくさい)」。指物(さしもの)師が見せる技の一つだ。
「木によって癖が違うから難しいよ」。ウルシ、ナラ、クリ、コクタン。広葉樹は硬く、針葉樹は柔らかい。木と木の相性はまちまち。配色が多く模様が複雑なほど接合が難しい。「なじむようにわずかに湾曲させたり、複雑な形に加工したり、試行錯誤だね」
机や椅子といった家具から筆箱などまで、県産材を主に組む。素朴な色合いは東京下町の江戸指物に由来する。初代で養父の故義男(よしお)さんが東京で創業し、戦後に宇都宮で工房を構えた。その伝統を2代目として受け継ぎ、根付かせる。
「挑戦ですよ」。伝統工芸といえども、生活の中で使われなければ途絶えてしまう。最近はスマートフォンのスピーカー製作にも挑戦した。中学生の孫から助言を受けることも。だが、次代への継承は一筋縄ではいかない。「こうした技を表現する道具も少なくなっている。刃物職人が減っているから」
古きを受け継ぎ、新しきに挑む。大量消費社会の中で、長く大切にされる指物を。日々、木と向かい合っている。
指物 金くぎを使わず、外から組み手が見えないように組み立てる木工品。家具が普及した江戸時代に発展した。伝統の組み方は何百通りもある。装飾の木彩は、寄せ木細工の一種。
 ポストする
ポストする