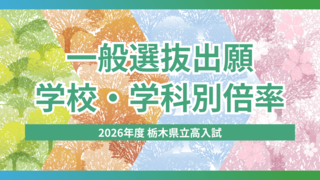本県の風土と県民の生活の中で育まれ、受け継がれてきた県伝統工芸品。後継者育成や次世代への継承などを目指し、県が2004年にスタートした「県伝統工芸士」の認定制度も今年で丸20年となる。現在は173人が認定され、県指定58品目の伝統を守る。昔ながらの高度な技術や技法で、工芸品をつくり出す認定工芸士の仕事ぶりや思いなどを紹介する。
太さの異なるヨシを一本一本、手の感覚で見極めていく。静寂の中、作業場には一定のリズムで機械の音が刻まれる。
よしず作りはかつて、農家が自分の家で使用するため、畑仕事ができない冬場に内職として行っていた。高度経済成長期になり、労働形態の変化で作る家庭が減っていったという。
渡良瀬遊水地に自生するヨシの刈り取りは12月から3月まで。水分を含まず十分に乾燥したタイミングで行う。曲がっているものはないか、割れているものはないか、現場で選別作業をするため、朝から日が落ちるまでかかることも。
「強風の影響で、刈り取っても半分が駄目だったというケースもある。自然に生えているだけあって扱いは大変」と話す。
皮むきなどの下処理を行いつつ、もう一度長さや太さを選別。できるだけ真っすぐなものを選び、一本一本に目を光らせる。雨風にも強いシュロ縄を使い、すき間がないように編む。形をそろえるため、機械には太さが違う根元からと穂先から、交互に入れている。
完成品は丈夫で見た目も美しい。「ヨシも何も見たことがない状態で嫁いで、製造に携わり50年以上。残せるうちは残してほしい」と願う。
渡良瀬遊水地よしず 日よけや雪囲い、防砂のほか、ホテルなどの装飾として、1年を通して需要がある。長いものでは10年近く使用できる。
 ポストする
ポストする