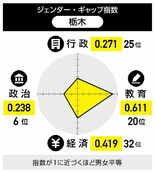温暖化などによるコメの高温被害を防ぐため、栃木県は2024年度、高温耐性がある県産オリジナル品種「とちぎの星」の栽培試験を西日本で実施する。気温が高い地域の特性を分析して栽培技術の向上につなげ、県内での作付面積を増やしていきたい考え。事業費として同年度当初予算案に140万円を計上した。
県農政課によると、栽培試験は西日本の複数の自治体に打診し、調整を進めている。具体的な試験地の場所や数は未定という。
本県より比較的温暖な西日本地域で栽培試験をすることで、同品種がどの程度、高温に耐えられるか、高温になる時期が本県と異なる場合にどのような影響があるのかなど、さまざまな気象条件下で栽培データを集める。高温下での水管理や農薬の使い方など、より良い栽培方法を見つけ、現行の栽培マニュアルに新しく盛り込む方針。
とちぎの星は県農業試験場が高温や病気に強い品種として開発し、15年に品種登録された。大粒で多収が見込め、炊飯後も粒が崩れにくいことなどが特長とされる。
昨夏の猛暑の影響で、23年産米の1等米比率は全国的に低迷した。一方、農林水産省の昨年末時点の検査結果によると、本県産とちぎの星は検査数量約3万トンのうち、1等米比率は93.1%となった。県内で一番多く生産されているコシヒカリは検査数量約10万トンで、同比率は86.0%。県産米全体では84.2%だった。
今回の栽培試験は県内でも気温が高めの県南、県央地域を中心に、とちぎの星の生産拡大につなげるのが狙いだ。猛暑でも安定した品質と収量が期待できる品種として、温暖化でコシヒカリなどが作りにくくなった地域で栽培の転換を進めていく方針。
同課は「西日本での試験結果を今後の栽培上のポイントとして活用し、高温下でも農家に安心してとちぎの星を作ってもらえるようにしたい」としている。
 ポストする
ポストする