「“災害”をどう伝えるか」がテーマの分科会は、能登半島地震での対応などを中心に議論した。
能登半島地震では被災地に向かう幹線道路で大渋滞が発生した。車列には取材車両も少なくなく、北國新聞社の宮本南吉(みやもとなんきち)氏は「使命感に基づく行動でメディアスクラムに似ている。限られた交通容量をどう使うべきかという視点も重要だ」と問題提起した。

日本テレビ放送網の小林景一(こばやしけいいち)氏は、車中泊見送りなど能登半島地震の初動取材時に設けたルールを紹介。「被災者に少しでも迷惑やストレスをかける取材はあってはならない」と訴えた。
災害ボランティアが秩序化されている現状を取り上げた大阪大大学院の渥美公秀(あつみともひで)氏は「能登では多様な人々による多様な活動を失った」と話す。東京都の宮地美陽子(みやちみよこ)氏は「災害時のデマは過去も繰り返されている。関係機関が連携協力し、偽・誤情報を共有することが大切」と強調した。
東日本大震災以降、福島県からの避難者を取材してきた茨城新聞社の綿引正雄(わたひきまさお)氏は「福島の問題を人ごととしない関心の想起を後押しし、風化を防ぐ」と報告。死者・安否不明者の氏名公表についてNHKの渡辺健策(わたなべけんさく)氏は「自治体の対応に差がある。災害の教訓検証という公益性への理解が不足している」と指摘した。
■座長
綿引正雄氏(茨城新聞社報道部デスク)
小林景一氏(日本テレビ放送網シニアフェロー)
■講師
渥美公秀氏(大阪大大学院人間科学研究科教授)
宮地美陽子氏(東京都知事政務担当特別秘書)
■報告者
宮本南吉氏(北國新聞社編集局主幹)
小林景一氏
綿引正雄氏
渡辺健策氏(NHK放送文化研究所)
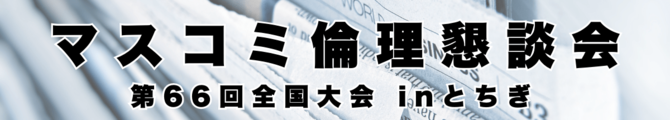
 ポストする
ポストする

















