今は九月の下旬。来年秋からB3に参加できるといっても、それはあくまでも机上の計算で、実際は不可能に近い。そもそも奨吾(しょうご)たちは公務員であり、民間のバスケットボールチームの運営になど参加できない。スポンサーとしても無理だ。地方自治体が営利目的のためにプロスポーツチームを経営するなど、あってはならない話なのだ。
「ちなみに四国にチームは?」
「ございます。B2に愛媛オレンジウォリアーズ、B3に徳島ナルトガイズと香川ホワイトヌードルズがあります。残念ながら我が高知県にはありません」
「なるほど。もしB3リーグにチームを作ったら県内初、さらにB1まで昇格したら四国初ということになるんやねや?」
「その通りです」
政治家というのは初モノが好きだ。県内初、四国初、全国初。そういう箔(はく)をつけたがる人種であると奨吾も知っている。しばらく資料を眺めていた永川(ながかわ)が顔を上げた。
「面白い。やってみるがよ」
「へっ?」
思わず変な声が出てしまったので、咳払(せきばら)いをしてから奨吾は言い直す。
「えっと、何とおっしゃいました?」
「やってみろ、と言うたがじゃ」
予想外の反応だ。きっとあっさりと却下されるものだと思っていた。最終的に妥協案として奨吾が考えていたのは、解散した高知クロシオンズへの行政的な支援だ。たとえば練習場所の提供などを持ちかけ、将来のB3入りを支援するというものだ。クロシオンズがB3入りした暁には、全国的な注目を集めることを期待して。
「ですが、市長。私は公務員としての立場上、民間のスポーツチームに肩入れできないわけでございまして……」
「そこに頭を働かせるのが君の仕事ぜよ、赤羽(あかばね)君。やりようはなんぼでもあると思うがな」
「そう簡単におっしゃられても……」
よもやの展開に奨吾は混乱する。
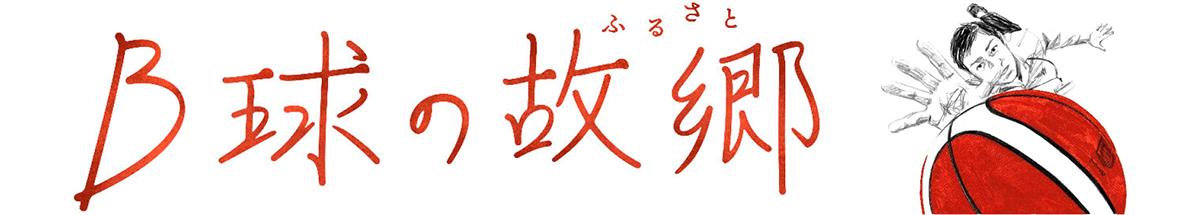
 ポストする
ポストする



















