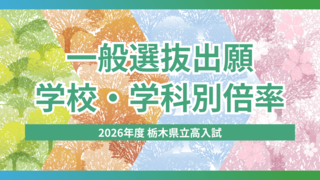夏の風物詩「灯籠流し」が17日夜、栃木県足利市永楽町の渡良瀬川河川敷で行われ、慰霊の思いを込めた約2千個の明かりが川面を照らした。
灯籠流しは1947年9月の「カスリーン台風」で市民らが甚大な被害に遭ったことを受け、台風の犠牲者と河川の安全などを祈る送り盆の行事として50年に始まった。市内17寺院でつくる「足利仏教和合会」が、毎年8月17日に行っている。新型コロナウイルス禍による中止もあり、今年で72回目という。

人々の思いが込められ、川面を照らす灯籠
日が暮れ始めると、家族連れらが河川敷に集まった。工事中の中橋と田中橋の間に設けられた祭壇で僧侶が読経する中、参加者は六角形の灯籠を川へ流し、静かに手を合わせた。
会の幹事を務める福厳寺前住職の采澤良俊(うねざわりょうしゅん)さん(73)は「時代が変わっても、先祖を慰霊する気持ちは変わらない。この行事を守り伝えたい」との考えを明かした。
 ポストする
ポストする