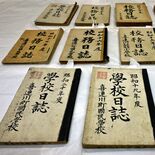「本当に肉片だったのかな」。原稿に目を通したデスクの問いに即答できなかった。
1945年2月10日に足利市百頭(ももがしら)町で起こった「百頭空襲」を取材した。8歳で体験した同町、岡村良司(おかむらりょうじ)さん(88)に話を聞いた。
サイレンが鳴り、家族と庭の防空壕(ごう)に逃げたこと、壕の中では曽祖父が祈りをささげていたこと、爆撃で母屋がつぶれたこと-。数々の証言の中でも、親戚の「肉片」を見つけた話が衝撃的だった。
空襲の数日後、焦げたような茶色の塊が道端に落ちていた。手に取ると、爆撃を受けて亡くなった消防団の親戚のものと直感したという。記者に向かって、うなじの近くに手を当て「首の所、耳の下のこの辺の肉だった」とよどみなく説明してくれた。初めて戦争がリアルに感じられた。
当初は衝撃そのままに、茶色い塊を首の一部と断定して原稿に盛り込んだ。果たして事実なのかという問いは、頭の中になかった。
取材は通常、対象者の話や資料から得られた事実を積み重ねる。一方、戦争体験者の取材では、個人の記憶や証言に頼るところが大きい。証言を忠実に書くか、客観的な証拠のない内容は発信せざるべきか。岡村さんの熱量ある語り口は信じるに足りると感じたが、証言以外に根拠はない。
思案の末、記事には「人間の首の一部とみられる肉片」と書き込んだ。凄惨(せいさん)さを物語る経験者のエピソードとして、戦争を体験していない読者に伝える上で要になるとの思いに至ったからだ。
80年前の一個人の体験を証明するのは不可能に近い。だが、記憶に耳を傾け、記者として解釈し、その人の脳裏に焼き付いた揺るぎないものとして伝えることはできる。体験者の声が聞こえなくなるまで続けていきたい。
(報道部 平山紗也華)
戦後80年。戦争体験を直接聞く機会が失われつつある中、下野新聞社など地方紙20社が連携し、各地の体験者の貴重な証言を共有する「あの時私は」を展開した。全国の地方の隅々で、戦争のせい惨さを目の当たりにした体験者から話を聞き、エピソードを掘り起こした各紙の記者が取材を振り返った。

 ポストする
ポストする