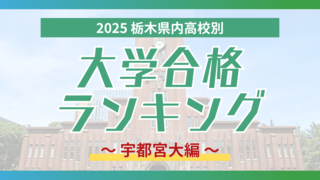-栃木県のイチゴ生産の強みを教えてください。
「54年連続生産量日本一の大きな要因は、全国唯一のいちご研究所でオリジナル品種を開発したことだ。クリスマスに間に合う出荷を可能にした女峰。生でも、加工でも良い万能イチゴのとちおとめ。観光いちご園で人気のとちひめ。夏秋イチゴのなつおとめ。高級品種のスカイベリー。多彩なラインアップをそろえ、しっかりとファンを獲得している」
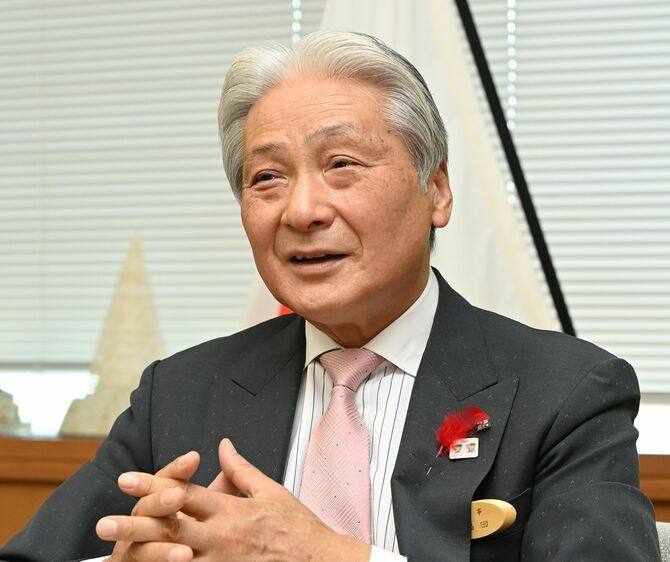
-2020年に名称が決まったばかりの「とちあいか」をどう評価している。
「甘く、おいしく、収量もとちおとめより3割多い。日持ちがする上、高温や病害虫にも強い。まさに本県イチゴのエースにふさわしい品種だ」
-本年度、今後10年間の「いちご王国・栃木」戦略を打ち出した。狙いは。
「将来の目指す姿を明らかにする必要があると考え、生産者と農業団体、県で策定した。2027年産までに、とちあいかの作付面積を県全体の8割にまで拡大することが核だ。その上で担い手戦略、生産戦略、ブランド戦略に取り組む」
-戦略の1番最初に担い手育成を据えた理由は。
「県内の生産者は2020年で1862戸と、10年前より17%も減った。県内外から人材を呼び込み、活躍してもらうことが重要だ。市町やJAなどの関係機関と一体で、希望者に農地、施設、住居などの情報を提供し、個々の状況に寄り添ったオーダーメードの支援をしていく。10月には、情報発信のウェブサイト『トチノ』も開設した」
「マンツーマンで指導するベテラン農家を『とちぎ農業マイスター』として任命し、技術指導を強化する。栃木県農業大学校に新設したいちご学科でも実践的な教育をしていく」
-生産戦略では、先進農家の10アール当たりの収量を3倍増にするという目標を掲げた。
「デジタル技術は生産量や品質の飛躍的向上に寄与する。人工知能を活用し、クリスマスやひな祭りなど(需要の高い時期に)品質の良いとちあいかを狙って出荷する技術開発に取り組んでいる。汎用(はんよう)化されていないが、(収穫用などの)ロボット活用も考えていかなくてはいけない」
-販売やブランドの戦略は。
「西日本やアジアなど、『西方2戦略』が大きな課題の一つ。プロモーションでの認知度向上は成果を上げつつあるが、生産量は変わらないので、関東で売る分を関西に持って行っているようで申し訳ない。とちあいかを増やすことで(本県全体の)収量を上げ、東京や関西、海外でもさらに売っていきたい。(ネット上で)影響力のあるインフルエンサーの『いちご王国アンバサダー』の任命や、関西圏への物流網構築、海外でのトップセールスなどを通じて絶対的なブランドの確立に努めていく」

-今後の品種開発に求められる役割は。
「とちあいかは『スーパーイチゴ』だが、それ以上においしく、生産者が作りやすい品種を目指す。1年を通して出荷できる品種や、輸出に適した味も見栄えも良く、日持ちする品種も開発したい」
「温暖化が進めば、今世紀末、栃木県の気象条件は今の九州地方と同じになるという。気候変動にかかわらず、収量、味、見栄え、病気に強い品種を開発することが課題。いちご研究所の役割は大きい」
-一方で品種の海外流出は懸念材料だ。
「本県も危機感を持っている。県育成品種が海外に持ち出されないよう、とちあいかやミルキーベリーについて、輸出が想定される国などで品種登録を進めている。また本県育成の5品種について海外への種苗持ち出し禁止を国に申請した。名称についても保護するため、とちあいか、とちおとめなどの商標権について、東アジア、東南アジアなど主要な輸出国を優先して取得している」
-二大産地と評される福岡県はどのような存在か。
「福岡県には、販売戦略や輸出で負けている。産出額は(栃木県と)7億円しか差がない。小さな面積で効率よく栽培し、高値でおいしい物を売っている。われわれはそこに追い付かないといけない」
「ただイチゴの消費量が減る中で、『多く食べてもらいたい』という考え方は同じだと思う。ライバルであり、パートナー。切磋琢磨(せっさたくま)する格好の相手だ」
-栃木県が目指す将来像は。
「量、質、加工、輸出、さらには観光と、あらゆる分野でイチゴ産業をリードしたい。国内のみならず海外でも、『イチゴと言えばTOCHIGI(とちぎ)』と言われるようにしていきたい」

 ポストする
ポストする