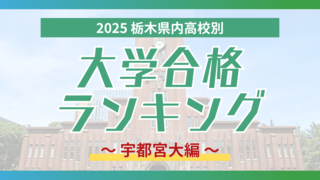-「あまおう」の本格販売から20年を振り返り、県が果たしてきた役割は。
「当時の福岡のイチゴ『とよのか』を超えようと、県の試験場が6年かけて開発したのが『あまおう』だった。イチゴ専門の普及員を置き、農家に生産技術を指導。ハウスなどの施設整備も県の単独助成で支援し、3年でほぼ全てのイチゴ農家があまおうに切り替えた。日本でもあまり例がないのでないか」
「品種の転換にはリスクもあり、思い切った政策だったと思う。『福岡のイチゴはあまおうでいく』という明確な旗を県が立て、生産者、JAグループなどの関係者と一体で進めたことで今のあまおうが育った」

-あまおうの強みは。
「一つは『あかい、まるい、おおきい、うまい』という品種の魅力。ぱっと見の印象に加え、甘みと酸味のバランスが非常に良い。もう一つは生産を維持する産地の力、三つ目がブランド力で、プロモーションに力を入れてきた。質と安定した出荷量を保つこともブランド維持の必須条件だ」
-農家の高齢化など担い手維持が課題だ。県としての対策は。
「課題の一つはハウス内の作業のきつさで、朝から晩までしゃがんでの作業は負担が大きい。かがまずに作業できる『高設栽培』を導入し、収穫や選別、パック詰めなどを担うロボット開発を進めている」
「人材育成としては、新規就農者にベテランの技術を伝える新たな取り組みを始めた。収穫時の視線を可視化するアイカメラなど最新技術を生かし、既に就農されている方向けの学び直しの場もつくる。全体の技術力が上がるよう、県がシステムを作っていく」
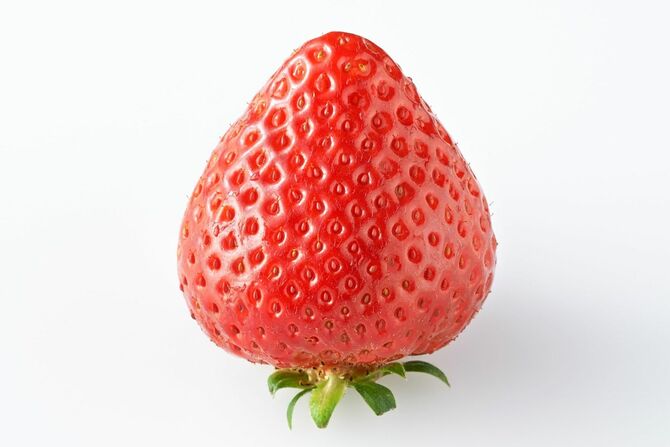
-栃木県の新品種「とちあいか」など、他の産地のイチゴはどんな存在か。
「競争があってこそ新しいもの、より良いものを生み出そうという熱が生まれる。産地それぞれの努力をして、われわれも負けないものを作っていく」
-あまおうに次ぐ新品種開発の可能性は。
「研究開発は常に必要だが、あまおうは販売単価日本一となるなど、今、変えるべき状況にはない。『イチゴの王様』の名に恥じないあまおうを消費者に届けることに努めたい。高品質の維持や生産力、ブランド力を強化し、輸出先の拡大も図る。『福岡のイチゴはあまおうでいく』という政策を守り、さらに強くしていきたい」

 ポストする
ポストする