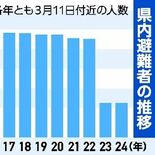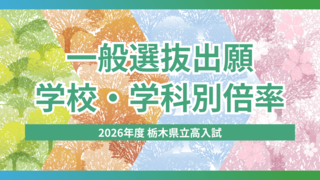海と生きる―被災者の今
13年たった今も、漁業関係者は震災や原発事故の影響を受け続けている。昨年から始まった原発処理水の海洋放出に対する受け止めや、心の復興のスピードはそれぞれ。福島の海の現在地は-。漁業や水産加工に取り組む2人に聞いた。
真の復興へ魅力発信
食卓には当たり前に魚が並び、道路には漁師たちの魚の落とし物がある-。水産加工業「上野台豊商店」を営む上野台優(うえのだいゆたか)さん(48)は「小名浜は魚であふれている町だった」と話す。あの日、津波で家と工場はほぼ全壊した。「やっていける自信がない」。母の言葉に自らを奮い立たせ、社長業を継いだ。
原発事故後、一時、売り上げは半減した。いくつも復興のためのプロジェクトを手がけた。青魚の栄養価の高さをPRし、料理人と子どもにも親しみやすいレシピを開発した。昨年には、いわき市観光物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」に直売店「小名浜あおいち」を開業した。

同じ年の8月、処理水放出が始まった。風評被害は思いのほか少なく、むしろインターネットでの販売額は前年同期の5、6倍に跳ね上がった。全国から強い支援の力を感じた。
だが福島での沿岸漁業の水揚げ量は今も、震災前の3割にも届かない。13年前の小名浜の風景や食文化を次世代に引き継げないとしたら-。「それは『復興』と言えるのか」。自問を胸に、福島の海が育む魚の魅力を発信し続けている。
魚の信頼回復に不安
愛船「第三政丸」で海へ出る。底引き網漁を営む志賀金三郎(しがきんざぶろう)さん(77)は50年以上、メヒカリやヒラメなどの「常磐もの」を追ってきた。
2012年、試験操業として、自粛していた漁が段階的に再開した。待ちに待った海の幸。近所に配ろうとすると、「子どもが小さいからいらない」と断られたこともあった。

苦難の中でも海と向きあい続けたからこそ、海洋放出は受け入れられない。「あれほど反対したのになぜ」。開始から半年足らずで、汚染水が漏出するなど人的ミスが起きる。築き上げてきたものが一瞬で崩れる思いがした。
処理水に含まれる放射性物質は国や東電が定めた基準を満たし、“安全”という説明を何度も受け、理解はした。でも消費者は本当に“安心”して福島の魚を食べてくれるのか。不安は消えない。
2年7カ月かけ、共に汗を流し海底のがれきを取り除いた仲間は半数近くが漁から離れた。それでも「網を引き上げ、旬の魚がバーッとかかっていた時の喜びは他には代えられない」。漁への熱い思いが自身を支えている。

 ポストする
ポストする